住宅の制度とシェアを再考する
──「HOUSE VISION2 2016 TOKYO EXHIBITION」
──「HOUSE VISION2 2016 TOKYO EXHIBITION」
日本人の暮らし方を「家」をプラットフォームに具体的に提示するために起ち上げられた研究と情報発信のプロジェクト「HOUSE VISION」。その2回目となる展覧会が、2016年7月から8月にかけて開催されました。テーマは「CO-DIVIDUAL 分かれてつながる/離れてあつまる」。過疎化や少子高齢化、細分化されたテクノロジーなどの今日的な課題を企業と建築家/クリエイターが協働で考察した12棟の展示ハウスを建て、日本の産業の未来を提示しました。また、会期中に開催されたトークセッションでは、さまざまな専門家によって本テーマが多角的に議論されました。本トークセッションでは「シェア」をテーマに、現代における家族や家という制度を問い直します。

SNSと都市の「おひとりさま空間」
土谷貞雄──今日は、建築構法を専門としながら、建築評論など建築学にまつわる幅広い活動をされている門脇耕三さんと、建築・都市と社会学の接点から相互を行き来する活動を展開している南後由和さんをお迎えしています。今日のテーマは「シェア」です。家族のかたちはいろいろと変わってきていますが、そのことと家との関係を紐解いていきたいと思います。まず最初にHOUSE VISION全体の感想から伺えますでしょうか。
門脇耕三──今日はすごくリラックスしているのですが、それはおそらく、この会場に木がふんだんに使われているからだろうと思います。使われている素材が、かつての未来像で描かれたつるつるぴかぴかしたものではなく、かつ全体の雰囲気も伝統的な家のあり方と切断されていない。むしろ農村的な雰囲気が復活している感じもあって、やはり未来の家とはリラックスできる場所なんだろうなと思いました。サルバドール・ダリは、ル・コルビュジエから未来の建築について聞かれ「それは柔らかくて毛深いものになるだろう」と答えたそうですが、この会場で使われているのは木と膜と電子テクノロジーで、未来の家がそういったもので構成されているということに、いよいよリアリティが出てきたんだなと思いました。今日は壇上の全員の服装がバラバラで、それもリラックスした雰囲気に一役買っていますし、同時に近未来的だと思います。
南後由和──会場の敷地である青海は、東京のなかでも居住という観点では場所性が希薄といわれがちなところですが、ここは現代的な集落のようで、ローカリティとは何かについて改めて考えさせられました。大東建託×藤本壮介さんの「賃貸空間タワー」はまさに集落のような形をしていますし、会場の端にあって高さもあるのでシンボル性を獲得していますね。今回のHOUSE VISION 2のテーマは「CO-DIVIDUAL 分かれてつながる/離れてあつまる」ですが、東京と地方で起こっていることを別々に捉えるのではなく、まさしく「分かれてつながる/離れてあつまる」循環として考えることが求められています。その際のキーワードのひとつは「モビリティ」です。会期終了後に吉野町へ移築され、新たなコミュニティやツーリズムの拠点ともなりうるAirbnb×長谷川豪さんの「吉野杉の家」には特にそれが現われていますね。

- Airbnb×長谷川豪《吉野杉の家》
©HOUSE VISION
原研哉──門脇さんと南後さんはHOUSE VISIONについて何度か批評をしてくださっていて、随分励まされます。前回の展覧会はインフィルが中心でしたが、今回は住宅産業というよりも、未来の世の中の問題をアクティブに捉えられる企業に入ってもらっています。ヤマトホールディングス、Airbnb、大東建託、三越伊勢丹などは、前回お声がけをしなかった企業ですが、家というプラットフォームを通して社会ヴィジョンを表わそうというお誘いに、リアルに反応してくださいました。
今回のテーマである「CO-DIVIDUAL 分かれてつながる/離れてあつまる」について言えば、平野啓一郎さんの小説『ドーン』(講談社、2009)には、「分人(ディヴィジュアル)」という概念が出てきます。これ以上分割できない「個人(インディヴィジュアル)」に対し、例えば学校の先生をしている私、彼女といるときの私、お酒を飲んでいるときの私......と、divideされた個がそれぞれあるという世界です。ばらばらになった個が共有する「Co-dividual」と、「シェア」の意味合いは異なると思いますが、今日はあえてその「シェア」というテーマで議論をしていただきます。

- 門脇耕三氏
南後──これまで仮面と言えば、本当の自分があって、「偽り」の自分もいるというネガティブな捉え方をされてきましたが、「分人主義」は、仮面の複数性自体をポジティブに捉えようとする考え方です。空間論に置き換えると、ひとりにつき一室という個室の捉え方に再考を迫るものでもあります。分人主義では、対人関係ごとに異なる複数の仮面があると考える。ただ、仮に分人の数が6だとしても、そのまま物理的な空間の数がリテラルに6になるというわけではありません。メディアに媒介されながら私が複数性をともなっている現在、近接と遠隔の関係を含め、個室という空間のあり方がどうなっていくのかを考えていく必要があると思います。
門脇──展示を通じて、AR(拡張現実)がリアリティを持ち始めていることもひしひしと感じました。最近リリースされた「Pokémon GO」も示唆的で、まさに情報空間での出来事が現実の都市に本格的に干渉しはじめている。実際にはこうした事態はだいぶ以前から進行していて、例えば現在の交通網はGPSによって支えられていますが、「Pokémon GO」もGPSを応用したARのひとつです。しかし、情報空間が都市や住宅をどう変えるのかはまだ誰もわかっていませんから、「HOUSE VISION 3」のテーマになるのかもしれません。
南後──社会学者は、ある対象が、過去から現在へとどう移り変わってきて、これからどう変わっていくだろうかを考える歴史的アプローチを重視します。これから、近年の「シェア」の議論における「みんな」や「開放性」を求める指向ではなく、その一歩前の段階にあった、個の自由や独立性を重視する指向について話したいと思います。つまり、シェアの時代に入る少し前の、1990〜2000年代にあった個をめぐる快楽や独立性を僕たちは易々と手放していいのだろうかということです。
日本建築学会が発行している『建築雑誌』の2015年1月号で「日本のおひとりさま空間」という特集を編集委員として担当しました。その内容を簡単に紹介します。2010年の国勢調査では、単身世帯の数が夫婦と子どもからなる世帯を上回っていて、最も大きな割合を占めるようになりました。単身世帯には、10〜20代はもちろんのこと、高齢者も含まれています。いまやニューヨークのマンハッタンでは50%以上が単身世帯です。僕の関心は日本の都市における「ひとりの空間」の変遷について考えることにありました。「ひとりの空間」のひとりは、単身者と違い、結婚しているか否かを問うものではありません。日本の場合は、1970〜80年代にかけて投資型のワンルームマンションが増え、カプセルホテルも誕生しました。90年代後半以降は、インターネットカフェやまんが喫茶も台頭してきました。こうした日本の「おひとりさま空間」は、住空間も商業空間も、海外と比べて種類がとても充実しています。例えばヨーロッパで、ぱっとひとりで入れるレストランは意外と少ないです。『建築雑誌』の特集では、「一蘭」というひとり用ブースに区切られたラーメン屋や、ダーツやスカイプもできる複合化したネットカフェなど、日本の「おひとりさま」商業空間のフィールドワークをしました。
門脇──南後さんはまんが喫茶を使いますか。
南後──数えるほどしか使ったことがないですね。
門脇──僕はよく活用しています。大学の研究室が郊外にあるので、午前中と夕方に都心で打ち合わせの予定を入れると、そのあいだの時間は往復するだけで終わってしまう。都心にシェアオフィスを借りるのも手なのですが、それだと場所の融通が利かない。まんが喫茶は都心ならどこにでもあるので、そこで3時間くらい仕事をしてから次の打ち合わせに行くと便利なんですね。東京都では条例の関係で、まんが喫茶に入るために会員証をつくらなくてはならないので、僕の財布の半分くらいはまんが喫茶の会員証が占めています(笑)。

- 南後由和氏
ほかの「おひとりさま空間」として、「ひとりカラオケ」についても触れたいと思います。従来、カラオケは同僚や友達などと集団で行く場所でしたが、「ひとりカラオケ」専用の店では、ひとり用のブースが並んでいます。なかには「ひとりカラオケ」に2〜3人で行って、ひとりずつバラバラに利用するという使い方もされています。練習やストレス解消などにも使えますし、ドリンクバーもあって喫茶店に行くよりも安価だということで、朝方に来る人も多いそうです。これら以外にも、ひとり焼肉やひとり鍋など、従来は集団で利用されていたコンテンツが個人化しているという流れがあります。その一方で、従来は個に分断されていたものが、「シェア」をとおして集団化しているという逆の流れも起きています。例えば、ゲストハウス、読書体験を共有するソーシャル・リーディング、パウダールームやラウンジなどの共用スペースを充実させた複合トイレなどです。
携帯電話から常時接続のスマートフォンの時代となり、いつでも人とつながっていることが常態化しました。だからこそ、ひとりでいることの時間や空間がより貴重なものとされるようになりました。ところが、僕のゼミ生に、「ひとりカラオケ」について話を聞いてみたところ、ひとりでいるけれど、じつはつねにSNSで友達とやり取りしていたり、場合によってはネット上でライブ中継をしていたりするそうです。ひとりになるための空間のはずなのに、ひとりになれない空間になっているのがおもしろい点です。
「常時接続社会」においては、ひとりを取りまく物理的な空間にも変化が見られるようになりました。1990〜2000年代はまんが喫茶のように物理的な間仕切りで区切られていたおひとりさま空間が、2010年代以降、スマートフォンやタブレットによって随時パーソナルスペースを立ち上げることができるようになることで、物理的な間仕切りが取り払われた空間が増えるようになりました。例えば、大きなテーブルです。大きなテーブルは、グループでも使えるし、個人でもその一部を使うことで自分の居場所を確保できます。グループと個人が共存でき、空間の個人化と共有化のスイッチングが可能であることがポイントになっています。大東建託×藤本壮介さん《賃貸空間タワー》の1階には、大きなテーブルがありましたし、「湘南T-SITE」のスターバックスのように、グループでも個人でも使える大きなテーブルのあるカフェも増えてきました。
次に考えたいのが、「常態としてのひとり」についてです。SNSやeコマースなどの情報空間では、たとえ家族でも個人が異なるIDを持っていて、個人単位で履歴が残ります。例えば、父親は父親でさまざまなSNSのネットワークを持っていて、母親も母親で近隣に閉じない情報空間でのネットワークを持っている。そうすると、家族はさまざまな情報ネットワークのひとつの交差点やハブに過ぎなくなってきます。もはや家族という単位を捉え直す必要すらあるでしょう。そもそも1日のうち、誰しもひとりでいる状態があるという意味で「常態としてのひとり」という言葉を用いたのですが、誰かと一緒にいても常時接続の情報社会ではつねにひとりとして扱われるという意味も含まれています。
最後に「個建築」の系譜についてです。「古建築」をもじった造語ですが、ひとりカラオケやネットカフェの空間を見ると、最小限の空間にさまざまな装置が埋め込まれていることがわかります。ひとりカラオケではヘッドフォンがあり、音響を操作するパネルなどがあり、狭い空間でも居住性を高めるための工夫が見られます。こうした個人に対応した狭小空間である「個建築」の系譜には、草庵文学の鴨長明の方丈庵から始まり、1972年の黒川紀章さんの《中銀カプセルタワービル》、黒沢隆さんの「個室群住居」などがあります。狭い場所にあらゆるものを秩序だって詰め込んでいく志向は、榮久庵憲司の言葉を借りれば「幕の内弁当の美学」ですし、李御寧の言葉を借りれば「縮み志向」です。
方丈庵を例に出したのは、冒頭に触れた近接と遠隔や、集団との距離のとり方を考えるうえで興味深い事例だからです。鴨長明は山奥に引き篭もっていたわけではなく、数時間歩けば京都の町中に出られるところに住んでいました。たまに京都の町中へ降りて行き、町の様子を観察しては、それらに対する批評を交えて『方丈記』を書いていたのです。つまり、集団から完全に隔絶されていたわけではなく、距離をはかっていた。鴨長明は、千葉雅也さんの『動きすぎてはいけない:ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出書房新社、2013)の言葉を借りれば、切断だけでもなく接続だけでもなく、切断されながら再接続していたと言えるかもしれません。
また「個建築」に関して、「モビリティ」という観点から考えるならば、東京はほかの欧米の主要都市と比べて、都市部の面積が大きいという特徴があります。鉄道に依存した交通体系のため、終電後に自宅へ帰れない人たちが時間を過ごす場所としてカプセルホテルやネットカフェの需要が高い。東京にカプセルホテルやネットカフェのような「おひとりさま空間」の数が、ほかの国より多い理由のひとつには、このような東京の都市構造との関係があると思います。《中銀カプセルタワービル》も当初は通勤に長時間を要するサラリーマンの都心のセカンドハウスとしてあったわけです。ネットカフェも、「ネットカフェ難民」のような労働や格差をめぐる問題だけではなく、都市のモビリティと関係していす。
そもそも都市が農村と大きく違うのは、異質な個人が集まる場所であるということです。すでに江戸時代から江戸には単身者の流入が多く、単身者のための住空間や食空間として、長屋や屋台がありました。都市では住空間が狭小でも、住宅機能が外部化されたサービスを利用し、都市に寄生しながら生活することができます。ドイツの社会学の古典で、ゲオルグ・ジンメルによる「大都市と精神生活」(1903)という論考では、異質な個人、匿名的な関係下の他者に囲まれた都市における生活は、人間関係やサービスを貨幣価値に換算する計算可能性によって成立しているという指摘があります。都市では互いに、人格化された精神による直接的な「一次的接触」ではなく、非人格化された精神による間接的な「二次的接触」をするわけです。ジンメルの「大都市と精神生活」は19世紀後半から20世紀初頭の都市ついてのものですが、現代の都市にも通底する部分が多々あり、都市とは、異質な個人同士が集まって共同体をつくる実験室であり続けてきたことがよくわかります。
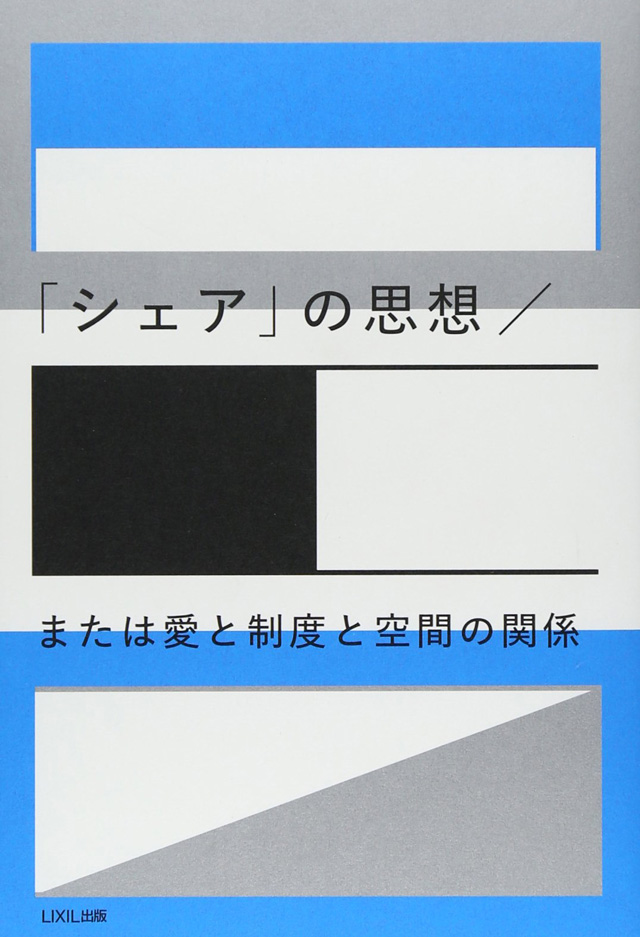
- 『「シェア」の思想/
または愛と制度と空間の関係』
(LIXIL出版、2015)
2000年代以降、未婚・非婚化や高齢化にともなって「おひとりさま」という言葉が流通するようになり、それに対応した独立性の高い「おひとりさま空間」が増えてきたわけですが、それらは商業ベースのおひとりさま空間、市場経済を介して入手可能な空間でした。今後は、消費を媒介とした個人同士のつながりのみではなく、生産やクリエーションを媒介としたつながりについて考えていくことが重要です。ただし、「おひとりさま空間」に見られた、個人の自由や独立性は手放すべきでも、犠牲にすべきでもない。シェアをめぐっては、「みんな一緒に」とか「開いていくこと」が強調されがちですが、もう少し「個であること」「閉じること」、あるいは『「シェア」の思想/または愛と制度と空間の関係』の門脇さんによる千葉さんへのインタビューでも言われている「秘密」を大事にしながら、「分かれてつながる/離れてあつまる」ことを考えていく必要があると思います。
門脇──南後さんがおっしゃるように、異質な個人がすれ違うことは、都市の本質なのでしょうね。僕の母親は「あの政治家は顔が良くないから信頼できない」というようなことを言いますが、英文学者の高山宏さんは、「邪なことを考えていると顔がゆがむ」(『表象の芸術工学』工作舎、2002)といった素朴な価値観がどのように発達したかを表象文化論的に論じています。「まったく知らない人とすれ違う」という状況は、産業革命以後のヨーロッパの都市で日常的なものになりましたが、それは人間に非常にストレスをもたらすものだったようです。そこで当時のヨーロッパでは、人間の顔をタイプ分けして、外観から内面までも判断できるとする「観相学」という学問が生まれます。この「外観は内面を表すメディアである」という一種の迷信は、その後のわれわれの価値観にも影響を及ぼしています。例えば雑誌では「性格をみがくと美しくなる」といった特集がよく見られますし、外観は内部の機能を素直に表象すべきであるというモダンデザインの思想も同根でしょう。ファッションについても同様で、現代人は服装からその人の趣味や価値観やライフスタイルを判断しますし、逆に自身の立場を表明するものでもあります。例えばスーツは社会人としてのビジネスマナーをわきまえていることの記号として機能していて、これを前提としてコミュニケーションが行なわれています。
しかし「異質な人どうしが一緒にいる」ことは依然として大きなストレスで、他者と物理的に切り離された空間はますます求められ、日本においては1980年代に完成度が高まることになります。このことは建築技術の発達とも無関係ではなくて、窓がなくても空気の清潔性が担保できる機械換気や機械空調が1980年頃には一般化し、外界から完全にシャットアウトできる空間が技術的にも可能になりました。南後さんからは、そうした「おひとりさま」状態の空間が、現在では建築的な技術や装置を使わなくても現出可能になっているという指摘がありました。ポータブルなデバイスを通じて情報空間に没入することで、外界はいつでもシャットアウト可能になり、結果としてスイッチング可能なプライバシー空間が都市や住宅の中で実現しつつあります。
南後──個に没入するための物理的空間として、建築的な間仕切りが必ずしも必要なくなっているというのは近年の現象だと思います。ただ、スマートフォンはひとりで没入しているように見えますが、じつはつねに他者とつながっています。
- SNSと都市の「おひとりさま空間」
- 家族という制度と家
- 秘密の空間、闇の空間の必要性


