建築の経験/写真の経験
たくさんの写真を撮ること
松原慈──新津保さんには、私たちが会場構成をてがけた日本科学未来館での展覧会「'おいしく、食べる'の科学展」の会場を撮影していただきました。まずはじめに、どうやって撮影していったのかを教えてください。新津保建秀──この展覧会を記録するときに意識していたのは、空間を一枚の絵で断定するのではなく、過渡的な状態で提示しようということです。
最初(午前中)は記録だからきちんと撮らなくてはいけないなと思って、しっかり水平をとってのちに資料としても成立するようにと、いわゆる建築写真的な造形上のセオリーをかなり意識していました。ただ、午前中に撮影してみて非常につかみどころがない空間だった。となると強度の高い一枚の画像で断定するのではなく、断片の集積によるとりとめのない流れのなかでとらえていったほうがよいと考えました。そこで普段行なっているようにある程度自分の勘にまかせて撮っていくようにしました。あとは、お二人が言葉をすごく重視されていたので、書籍や電子化されたアーカイブになったときにエッセイや誰かとの対談など、さらにはドローイングなどこの場を生み出す過程で生まれたさまざまな断片とリンクさせていったときに完成するようなイメージ群になることを目指しました。
松原──撮影をお願いするにあたって、私が新津保さんに打ち明けた悩みは、展覧会での体験をドキュメントしたいと思ったときの難しさでした。数枚の写真だけではうまく説明できないから、写真ではやらないほうが良いのだろうかなどと。でも、新津保さんが建築へ興味や関心を示していたときにちょうどお願いできたことが、こうした写真を生んだのだと思います。
有山宙──新津保さんのお仕事を拝見して、撮られ方の異なる二つの写真を、僕たちは〈午前の写真〉/〈午後の写真〉と勝手に名付けました。〈午前の写真〉で代表的なものは、建築雑誌に載っているようなちゃんとした建築写真で、それはそれでもちろん僕たちはリスペクトしています。ただ、そうした〈午前の写真〉だけではもはやコミュニケーションを取れない相手がいるのではないかと感じていて、まずは〈午後の写真〉の空間に対するアプローチについて建築に関与している皆さんと話したいと思ったわけです。それから、新津保さんや中山さんの住宅を撮影した岡本充男さんは、まさしく〈午後の写真〉のアプローチを取っていますが、もっとほかに違う空間のとらえ方もありそうな気がしています。今日は基本的に〈午後の写真〉にフォーカスしてお話しして、第三のアプローチについての意見交換もできればと思っています。
未来館の写真は、完全に〈午後の写真〉だと思いますが、だんだんとやる気がなくなってきている訳ではないんですよね?
新津保──そんなことはないです(笑)。
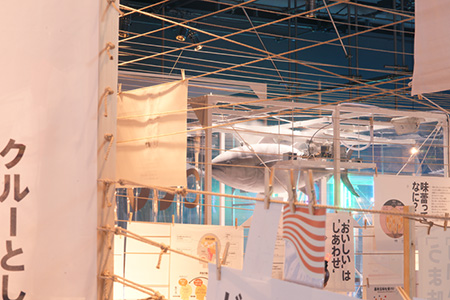

- 「'おいしく、食べる'の科学展」の会場風景
撮影=新津保建秀
松原──ここでドキュメントしているのは空間なのでしょうか。それとも時間ですか。
新津保──自分がこの場で過ごしたひとときをトレースして空間を撮れれば良いかなと考えていましたから、時間を手がかりにして空間をとらえていったということになるのかな。
ところで、未来館での撮影時の自分のなかのスタンスには伏線が二つあって、それは両方とも音楽に関わる作業でした。音楽家の渋谷慶一郎さんが主宰する音楽レーベルATAKからリリースされたi8U+Tomas Phillipsによるフィールドレコーディングを緻密に構成した音響作品のアルバム『ligne』のための作業と、渋谷さんが自身のレーベルから去年リリースした『for maria』というピアノのアルバムのレコーディング作業のドキュメントの撮影です。渋谷さんは電子音楽の世界で非常に知られている方ですが、昨年ピアノのアルバムを出したんですね。ここで自分はレコーディングの様子をずっと記録として撮っていました。元々自分はフィルムで撮ることが多いのですがレコーディングしている空間の光の環境が不安定で感度調整が難しそうだったため、初めて一眼のデジカメを買ってすべてデジタルで撮りました。フィルムの場合、ひとつの完結したメディアの中に時間を封じ込めていくような感覚があるのですが、デジタルで撮影する場合、茫洋とした大きな空間に際限のない断片を放り投げていくような感覚があります。このときは一枚の写真で言い切るというより、全部が溜まったときになにかが見えてくるような写真が撮れたら良いなと思いながらやっていました。ある種の電子音楽には非常につかみ所のなくはじめも終わりもないような音のテクスチャーだけでできているような音響作品があるのですが、こうした感覚を視覚化してゆくことにまえから興味があって数年前からいくつかの習作をつくっていました。その過程で、時間を過渡的に表記していくことへの興味はすでに醸成されていた気がします。
未来館では、被写体は建築空間なんですが、レコーディングの様子を撮っているのと同じようにすればいいなという気持ちで撮影していました。こうして撮った写真は普通のシンプルな記録写真なのですが、先行してやっていた撮影とテーマがつながったような気がしています。
松原──たくさんの写真で空間の体験を再現するという試みは、中山さんも試されていますよね。
中山英之──いまの新津保さんのお話は、自分が2〜3年ぐらい前に思っていたことをそのまま外から聞く感じで、嬉しいような恐いような気がしました。
僕が設計した住宅《2004》が出来上がってしばらくして、新しい家具を搬入することになって、ただ現地に行って帰ってくるだけではもったいないので、写真家の岡本充男さんに一緒に行きませんかと誘って来てもらいました。一日一緒にいて、僕は棚を取り付けていて、彼は35mmの手持ちのカメラを下げていたのですが、一日の仕事が終わっても写真を撮ってくれていたのかよくわかりませんでした。カメラをぶら下げていたのに撮っている印象が全然なかったのです。ところが、それから一週間ぐらいして、プリントされた写真をそのまま持って来てくれたのですが、写真の枚数が300以上ありました。いろいろと試行錯誤している感じもあまりなく、どんどん撮っているという感じで、彼が過ごしていた時間がそのまま映し出されているようでした。


- 中山英之《2004》
撮影=岡本充男
松原──私は、自分たちが設計した空間をドキュメントしてもらいたいと思って新津保さんに頼んだのですが、実際に写真の束を見てみると、知らないものが多く写っていて、まったく知らない記憶、誰かの記憶がそこにある感じで感動しました。うまくドキュメントがとれたというよりもむしろ他者の記憶が映しだされていたことに反応したのではないかと思うんです。中山さんが説明されていたような、この写真の束のなかに建築の経験がすべてあると読み替える感覚は、それが自分が求めていた空間のドキュメントであったというより、人が丁寧に体験した時間の流れを一遍に見ることができたから満足したということだと思っています。
中山──それは僕の抱いた感覚とすごく近いですね。
松原──空間の記述と言ってもいろいろなレベルがありますよね。誰の視点に立った空間の記述なのかということが問題になるし、そうすると私たち設計者がうまく記録できたと思う満足感っていったいなんだったのかと思ってしまいます。一方で、実感を大量の写真で見せるというのはすでに試したこともあって、私はどちらかというと、それとは違う方法があるのではないかとすごく気になっています。
新津保──写真というと光をコントロールするもののように思われますが、時間のコントロールが肝だと感じています。音楽関係の人たちと話していると時間を扱いながら空間を扱っているんだというようなことを耳にすることが多いのですが、そうしたことを行ないながら、写真以外の表記方法でも場所を記述することができるかもしれないですね。撮影と並行してフィールドレコーディングを行なうことがあるのですが、音が喚起する空間性は写真よりもその場をよくとらえている場合があります。
写真による前後関係の凝縮
有山──今回、事前にみなさんから何点か資料を送ってもらいました。山岸さんには、詩を送っていただきました。山岸さん読んでみますか?山岸剛──三好達治さんの「土」という詩ですね。
「土 蟻が 蝶の羽をひいて行く ああ ヨットのようだ」
ぼくは写真家ですが、自分の写真を考えるにあたって、小説家や詩人の仕事、その言葉のありかたにいつも大きな興味をもっています。この三好達治さんの詩は、平易で端的な、数もそう多くない言葉の連なりでしかありませんが、タイトルの「土」、行替えというルール、「ああ」という感嘆詞の効果などから、ほんとうに豊かな作品経験をもたらしてくれます。だれにでもわかる、簡単な一つひとつの言葉に、あらゆる次元のものが呼び込まれているようで、いま皆さんがおっしゃっていたような「時間」としか言いようのないものがはらまれているというのか、そういうものが詩という形式に統合されている、結晶化されているように思います。人によってやり方はさまざまだと思いますが、写真家というのは基本的に「量」をたくさん撮るわけです。そして、そのなかから選択する。ぼくはその選択された一枚一枚の写真に、いかに多くのものを呼び込めるかというのをつねに意識しながら写真を制作しています。被写体やその場所にいたときの感覚はもちろんのこと、いままでに見てきた写真やイメージ、記憶などといったものを一枚一枚の写真に凝縮していくような感じでしょうか。そういう意味では、結果的に、まさに「時間」を扱っていると言えます。

- 「上原通りの住宅(設計:篠原一男)、2009年12月8日14時」
撮影=山岸剛
松原──この人たちを知ってますか? ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニというドイツの写真家/映像作家です。彼らは必ず高解像度で撮影し、すごく大きいサイズで発表します。いわゆる建築写真っぽい写真ですが、建築の竣工写真ということではなくて、その建物の持ってるヒストリー全部を一枚の写真に凝縮しようとしている。例えば日本だったら長崎の軍艦島とか、変わった歴史のある建物や場所を被写体に選び、一枚で歴史を感じさせるような写真を撮ります。彼らも同じように時間を大切にしていますが、アプローチが違いますね。
有山──例えば、これは同じくニナとマロアンのフランスの図書館の写真ですが、これは〈午前の写真〉のように見えませんか。これは、改修前に本が全部なくなった時の写真で、一瞬竣工写真のように見えますが、廃墟なんですね。これは建築写真の形式をもった写真です。そんなことはないですか。
山岸──そうですね、そう言えると思います。だからこういう、いわゆる「建築写真」らしいものが、さきほど見せていただいたような大量の写真による経験に匹敵できないかというと、必ずしもそういうことはないのだと思います。いまふうに言えば、ネットなどで無意識的にたれ流されている、ほとんど洪水のような大量の写真群を、いかに作品としての写真に統合していくのかが、現代の写真家の仕事のひとつであると思います。もちろんそれは、一枚の決定的な、強い写真である必要はないわけです。

- Nina Fischer & Maroan el Sani, "Toute la mémoire du monde - BNF I"
Colour Prints on Alu-Dibond 124 x 150 cm Edition 3 ( + 2.e.a.), 2006.
URL=http://www.fischerelsani.net/
中山──話を膨らませすぎかもしれませんが、伊東豊雄さんの事務所で先輩だった平田晃久さんと話していて、幾何学のとらえ方の変化について、話題になったことがありました。あらかじめ均質で無限にある空間を想定して、そこに座標を打っていき、最後にそれらを結ぶというのが古典的な幾何学のとらえ方だったとすると、それでは「外部」が無限定のままになってしまいます。「外部」環境の有限さは、私たちみんなの切実な問題として無視できませんから、もう少し両者を等しく、あるいは連続的にとらえられるような考え方を探す必要がありそうだ。そこで出てくるのも、やっぱり時間です。ある時間軸のなかで変化し続けているものを、細部の無秩序に翻弄されずに全体的なつり合いを計ることのできる、そういう幾何学について平田さんは考えています。そういう幾何学は、ある瞬間を切り取って観察することにも耐えますが、その前後にある時間の流れみたいなものを、その瞬間が映しているようにとらえることができます。つまり、ムービーだから時間があってスチルだったら時間がないということではなくて、スチルを見ても、スチルが切り取っている世界の配分、バランス、釣り合いみたいなものを無意識に読み取ろうとしている。そうするとやはり数秒後・数分後の状況、あるいは同時に別の場所で起こっていることが気になる。それは、ここで切り取っているものというのはここだけの問題じゃなくて全体のつり合いのなかのひとつを見ているという視点があるからでしょう。
山岸──AARというウェブサイトで中山さんのインタビューを拝読しました。ぼくは建築の専門的なことはよくわかりませんが、コンピュータなどによるシミュレーションが高度化していって、先のことがある程度予測可能になったときに、建物をつくっている時間と、それを使う時間が連動してくるみたいなことをおっしゃっていましたよね。ぼくは例えば住宅の写真を撮るときには、この建物はどんな人が住むんだろうとか、この部分はどういうふうに使われていくのだろうとか、そういうことを一枚一枚に流し込むようなかたちで写真を撮ります。あるいは、「家」というものが根源的にもっているイメージ、例えば「押し入れは暗くて怖い」とか、そういったことも意識しながら撮る。そういうイメージの蓄積を写真の背後にしのばせる、というのかな。きわめてアナログではありますが(笑)。
中山──最近よく言っていますが、設計の過程にけっこう正確な未来予想みたいなものが、いろいろなかたちで入ってきています。例えば大きい地震が起きたら建物がどういう壊れ方をするのか、あるいは何百人もの人がいっぺんに入ってきて、それが真夏のお昼だったら室内の熱環境はどんな感じになるのかとか、そういう未来予想をもとに、それぞれに逐一対処するかたちでつくっていけるようになってきました。それがもっと進化して、よりはやく正確に未来を予測し始めると、「つくる/考える時間」と「使う時間」の区別がなくなっていくかもしれない。そうすると設計者は、これまでのような、未来を上手に予測する千里眼を持った山師みたいな人ではなくなって、むしろ設計する時間のなかで使ってる時間と同じような振る舞いを、設計者自身もはじめるようになるはずです。
少し抽象的な言い方でどこまで共有できているのかわかりませんが、このことは「設計している時間と使う時間のあいだに現われてきた新しい私」みたいなもので、見方によってはちょっとルーズに見えるかもしれませんが、さきほどのような撮り方をした写真には、それがちゃんと写っている気がなんとなく実感としてあります。
松原──空間をつくっていると、使う人とつくる人は一緒という感じがするんです。使う人が体験することを分けて考えようとすると、完成品というもののラインが決まってしまう。だけど、使う人の振る舞いはつくる人の振る舞いと絡み合った状態でしか存在しない。そしてそういう前提でしか設計はできないと考えることが多くあり、その絡み合った関係自体をドキュメントしようとすると、どうしても時間軸がいるんですよね。戸田さんは、建築というのは絶対にフレーミングできないものとおしゃっていましたが、そのこととも関係しているかもしれないです。
質感だけの写真
戸田穣──ここに、2007年のTNプローブでのレクチャー・シリーズ「建築と写真の現在」の記録をまとめた冊子があって、そのなかに新津保さんの写真も掲載されています。新津保さんは建物のファサードのテクスチャーだけを切り取っていらっしゃっていて、これを見たときに私が思い出したのが、バート・スターンという写真家によるマリリン・モンローの写真です。彼女が死ぬ数週間前に、写真家と彼女が二人っきりでホテルの部屋にこもって撮ったものなのですが、肌のテクスチャーがまざまざと出ていて、けっこう残酷なんです。同時に美しい写真でもあって、お腹には彼女の手術の跡なんかも見えています。新津保さんの写真にみられる建物のファサードのテクスチャーとか、私がマリリン・モンローを想起したように写真に表われる皮膚感といったものは、ひょっとしたら写真家もしくは建築家自身が興味を持つ対象なのかなと思っています。
松原──時間を撮ろうと思ったらきっと残酷ですよね。
戸田──写真という二次元の表面の厚みとでもいうべき部分にたぶん時間が現われるのだと思います。以前、松原さんに「建築というのは絶対にフレーミングできない」といったのは、そういった、写真に現われる時間をさしています。中山さんはとあるインタヴューで、設計の段階で時間を走らせているとおっしゃっていますよね。あるひとつの線を描くことから順番に設計していく段階で、最終の全体像が見えないまま設計されているというお話をされていて、それが不安ではないですかというような応答もありました。それを読んで、設計の段階で先の見えないままやっていくプロセスそのものが、建物に時間性を与えていくということなのかと思いました。同時に設計をどこかで終えることも、作家の決断として必要です。
新津保さんの1,369枚の写真にも、同じような印象を感じたので質問したいのですが、いつこれで充分だと思われて撮影を止めたのでしょうか。それは外在的な条件ですか。
新津保──その両方が拮抗するタイミングで筆をあげていたと思います。未来館の撮影は、撮る時間をあらかじめ決めていました。自分の場合これまでの経験でいつも9時から17時ぐらいまでが調子が良くて、それを作業の基本時間にしています。ですのでよっぽどのことがない限り、遅くとも19時には終えるようにしています。夜にペースが上がる人もいると思いますが、いろいろ試してみて自分の身体的なペースにあっているので、自分はそのペースを守ったということです。
松原──会場から「触覚についてどう思いますか?」という質問がきました。これはさっきのマリリンの皮膚の話や、新津保さんのFOIL GALLERYでの展覧会「Rugged TimeScape」とも関係しそうですね。
有山──では、新津保さんがFOIL GALLERYで発表された写真を見ましょう。
新津保──これは複雑系研究者の池上高志さんとの共同作業によって制作したもので、彼がいなくてはできなかったと思います。今回の作品では、風景の中の雲とか森とかの抽象的な対象を撮影した画像を、池上さんによって組まれたプログラムで自律的に解体したものです。さきほどから話題になっているひとつのプロセスの前後ということと関係するかもしれませんが、ここでは一枚の写真から膨大な変化のヴァリエーションが生成されます。
有山──ひとつの風景写真みたいなものを入れるとこういうさまざまなヴァリエーションがでるということですね。
新津保──そうです。写真や映像において多くの場合、いわゆる何が映っているかが問題になりますが、この写真作品ではそういうことに留まらない抽象性が主題になっています。
山岸──たくさん出てきたもののなかから新津保さんが選ぶということですか。
新津保──僕がある程度選びこんだ後に、池上さんとディスカッションしながら新たに画像変換をしたりして詰めていきました。音響作品の制作でサウンドファイルをお互いにやり取りするような感じに近いのかなと思います。展覧会と同時発売された作品集も同様です。この写真での作業と並行して、池上さんが2010年に3月にYCAMで発表した《MTM》という映像作品があるのですが、そこの実作業に向かう過程で話していくなかで共有できたいくつかの問題意識が反映されていると思います。
有山──選ばずに、はじめに出たものから時系列に並んでいるのもありますか。
新津保──ありますね。展覧会においては、その過程で吐き出されたものを時系列順に並べ一枚に統合した作品もあります。この作業ではSemitrasparent Designの田中良治さんに画像データの統合をお願いしました。
FOIL GALLERYの展示は、さっきお話しした渋谷さんと相対性理論による『アワーミュージック』というプロジェクトのための写真作品をつくることがきっかけになっています。もともとは流体=煙の写真でやろうかと話していたのですが、池上さんとやってみたら面白いんじゃないかという意見が出て、池上さんのプログラムをとおしたところ非常にイメージにあったものが生まれました。


- 新津保建秀+池上高志「Rugged TimeScape」展(@FOIL GALLERY)での展示作品
松原──撮影したものを、ブラックボックスに入れてそこからなにかに翻訳された大量の結果が出て来て、それを自分で選ぶということは、二回シャッターを押すようなものですね。
新津保──確かにそうですね。個人的には写真の面白さは概念的なことにしろ、技術的なことにしろなにらかの構造を設定することでこれまで周囲に偏在していたものの見過ごしていた事象がパッと立ち上がる瞬間にあると思います。そのあたりの意味を少し拡張することに興味があったので、この作品では写真の作業でイメージを立ち上げるためのフレーミングと画像形成のプロセスを包含したものとしてこのプログラムをとらえていました。
さきほどから時間のことが話題になっていますが、2008年に『GOTH/モリノヨル』という猟奇殺人犯が登場する小説の書籍のために使う写真を撮影したときがあるのですが、ここでは都内のあるいわく付きの街を選んでいます。このとき場所が持つ気配が周囲の空間に波及していると時間を感じるなと思いました。このプロジェクトで街を撮るにあたって、そこで起きたことを入念にリサーチしたのですが、その過程では、視覚的な情報とは別のレイヤー上で、ネット上での人の噂や、googlemap上の不審者情報など、言葉の連関から立ち上がってくるある種の風景というのがすごく興味深かったです。その翌年の2009年に相対性理論とのプロジェクトでのメンバーがまったく写っていないアーティスト写真の依頼を受けたときもその『GOTH』と同じ場所で撮っています。
ぼくが、相対性理論というバンドを良いなと思ったのは、なにか今の社会に充満する視線の不穏な感じがあったからなんですよ。一見可愛いんですが。彼らの歌で立ち上がっている風景はまったく映像を使わずとも、国道沿いに看板と大型店舗が林立する風景の裏で一体なにが起きているのかわからないような、不気味で不穏な空気が感じられます。空間とか街は、写真や映像のような光学的なアプローチと生成変化する言葉の連関とが繋がることで、面白い立ち上がり方をするのだなと実感しました。
今回の記録写真に話をもどすと、それ自体が単独で機能するよりも自分以外の誰かの手による何かほかの断片と結合してゆくことでより豊かに空間を記述できるものになれば、と願っています。
松原──リチャード・アヴェドンがポートレイトを撮るときも、丹念にその人のことを調べ上げて、撮る時間は30分ぐらいであっても、そのポートレイトを撮る瞬間は彼が決めることができて、しかもその瞬間を意図的につくろうとしたそうです。写真家はそんなふうに建物や風景に対してもそのアクションを起こすことができるだろうし、いろいろなレヴェルの観察に基づいてそのアクションができるだろうなと思っています。そうすると大量の写真という方法だけではなく、建築だったりなにかスタティックだと思われているようなことの前後関係みたいなものを浮き彫りにしてしまうような、そんな残酷な写真はありうるのではないかと思うのです。
[2010年4月1日、FLAIR POOL@南洋堂書店にて]
FLAIR POOLとは、APRIL FOOLのアナグラムであり、2010年4月1日に南洋堂書店を会場に行なわれたassistant主催による「空間と写真」をテーマにした公開勉強会の名前である。写真家、建築家、建築史家が話者として参加したこの集まりを、トークイベントではなく勉強会という扱いにしたのは、すでにもっている知識や取り組みを数時間で交換するだけでなく、イベント前後の議論自体をを発展させることに焦点を当てたからである。事前に話したことと当日話すことは等価に扱うという前提のもと、個人的に国内外の建築家、ジャーナリスト、アーティストらと交わしたテーマに関連する会話はその一部を映像資料として上映し、各話者と事前に議論した内容は、この日の伏線として配布資料にまとめ、会の最後に聴衆に手渡した(編集=古賀稔章)。会の最中は、話者は聴衆と別の階におり、目の前に不在であったが、書店のガラスファサードに向けて、4つのスクリーン(話者の中継、2種類のスライドショー、ウェブカムでリアルタイムに閲覧される参考図書)を同時に投影し、上下階を移動するメッセージカードを使って話者と聴衆の遠隔対話を行なった。なお、本勉強会のストリーミングはされなかった。
松原慈(assistant)
●FLAIR POOL
企画=unfold with assistant
協力=Geoff Manaugh(ジャーナリスト/BLDGBLOG)、Nina Fischer & Maroan el Sani(アーティスト)、Brooklyn Digital Foundry(Digital Media Design Firm)、西田司(ON design)、狩野哲郎(アーティスト)、田村友一郎(アーティスト) 木戸昌史(Whatever Press)、古賀稔章(編集者/fold/unfold)、斉藤歩(編集者/M/M)、南洋堂書店
URL=http://www.withassistant.net/absentschool/index.html


- FLAIR POOL会場風景
しんつぼ・けんしゅう
1968年生まれ。写真家。写真とフィールドレコーディングを主体とした制作活動を行なう。作品集=新津保建秀+池上高志『Rugged TimeScape』(FOIL、2010)。http://www.kenshu-shintsubo.com/
なかやま・ひでゆき
1972年生まれ。建築家。中山英之建築設計事務所主宰。作品=《2004》ほか。著書=『中山英之/スケッチング』ほか。http://www.hideyukinakayama.com/
やまぎし・たけし
1976年生まれ。写真家。2010年より日本建築学会会誌『建築雑誌』編集委員。「オン・サイト」として写真作品を連載中。
とだ・じょう
1976年生まれ。日仏近代建築史・庭園史。博士(工学)・東京理科大学PD研究員。翻訳=クロード・パラン『斜めにのびる建築──クロード・パランの建築原理』。共訳=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』ほか。
まつばら・めぐみ
1977年生まれ。建築家。2004年ロンドン大学バートレット建築学校MA修了。assistant共同主宰。表現活動の幅は、静的な建築から、つかの間の状況まで多岐にわたり、空間造形、彫刻、音楽、文章、建築、都市研究などの分野で複合的に観察できる。http://www.withassistant.net
ありやま・ひろい
1978年生まれ。建築家。2003年東京大学大学院建築学科修了。2004-05年Alsop Architects, Ushida Findlay architects(ポーラ芸術財団の助成)。assistant共同主宰。http://www.withassistant.net


