生環境の環を歩きながら
「地球の声」に耳を澄ます
「地球の声」に耳を澄ます
下部構造としてのEarth Life Mode

- 青井哲人氏
この頃のシカゴの建物は、まだバルーンフレーム構法でした。アメリカ大陸を西部へと開拓する際に原生林を切り拓き、水位差を生かした動力で2×4材と板材を大量に製材する。これを組み立てるのに熟練労働は要らないわけで、アメリカに適しており、住宅だけでなく3〜4層前後のオフィスもすべて木造のバルーンフレーム構法でつくられました。地球、大地の資材化から一定の産業的編成へと進むとはいえ、まだ鉄や石油を使う産業化ではない。シカゴでは、ミシガン湖が雨で増水して街がしょっちゅう水に浸かるので、日本でいう曳家業が活躍しました。「The Lifting of Chicago」という論文によると、オフィスをジャッキアップしたり、富裕層が郊外に居を移す際に曳家が用いられたりしました。この状態を一変させる契機になったのが1871年のシカゴ大火による都市の全焼です。よく知られるように鉄骨造の高層ビルへのシフトで、土地の造成を行い、深い杭を打つことがはじまる。この流れの先にシカゴ派が登場する。これ以前に製鉄産業の集積がやはり五大湖周辺の水系に発達しており、数億年前に生み出された地中の鉄が掘り起こされるのですが、これと都市が、大火をきっかけに出会ったことになります。先ほど話に出たカレドニア造山帯の端がちょうどミシガン湖周辺に当たるわけです。
インディオの集落形成は原理1、そこに商人資本やバルーンフレームなどの原理2の構築技術が接合し、ついで鉄を使うことで地表の桎梏から解放されるけれど、それは同時により地球のより深い資源へのアクセスを全面化することだったわけですね。これが原理3へのシフトです。こうした段階論の探求は、マルクスにも柄谷にもなかったものを議論に組み込むことになると思います。

- 松田法子氏
塚本──生環境は英語だとどのように訳すのですか?
青井──少なくとも英語と中国語で伝わるようにしたいのですが、まだしっくりくる訳語に行き当たっていません。「生環境」をそのまま中国語で使うと「生きた環境」という意味になってしまう。英語の「Living Environment」は人が生きるための環境という意味にしかならない。どちらも私たちの提案を表現できません。そこでひとまず英語の暫定案として「Earth-Life Mode」というタームをつくってみました。Modeはマルクスの「様式」です。マルクスは「生産様式(Production Mode)」、柄谷は「交換様式(Exchange Mode)」です。これらの下部に地球の自律運動を敷き込んで再検討する、というのがこのプロジェクトの要点です。そこで地球の運動と人間がつくり上げる構築環境とのコンプレックス(複合)ないしレジーム(体制)をEarth-Lifeという表現で捉え、そのモードの転換を構想する、というように考えたわけです。
「量としての人間」が変えるもの
中谷──鉄の話については、生環境の研究を始める前から日埜直彦さんと議論していた経緯があります。すこしコメントをいただけますか。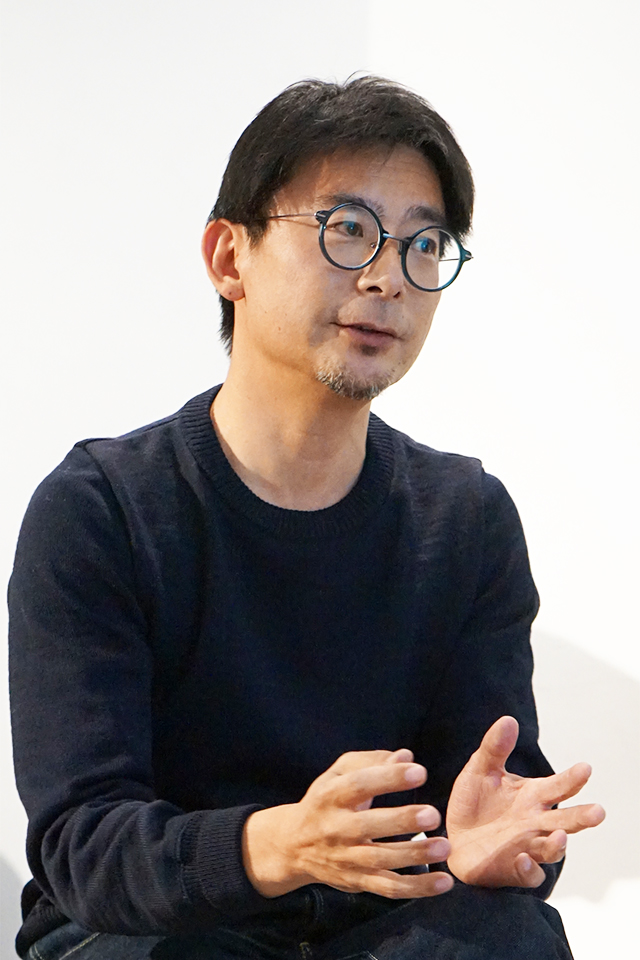
- 日埜直彦氏
地球物理学の見ている地球の歴史も、不可逆なプロセスですね。鉄のことで言えば、原始の地球上に、はじめて光合成をおこなう生物である藍藻が登場することで酸素が大量に大気中に放出され、海に溶けていた鉄が酸化鉄になって海底に降り積もる。それがつまりいま人間が採掘している鉄鉱石、縞状鉄鉱床をつくったわけです。藍藻誕生以降は地球の大気に酸素が含まれ、そのことで地球の様相は不可逆に変わってしまった。そして藍藻が地球を変えたように、おそらく人間だって地球を不可逆に変えていると考えるべきじゃないか。おそらく、どころではなくて、つまりそれが環境問題であり、あるいはいわゆる人新世ですね。そういうことで、円環が閉じるというよりはむしろ別の状態にドリフトしていくことを想定しているわけです。
それでこの問題でもうひとつ言うと、「量としての人間」ということを考える必要もあるように思います。人間が10億人くらいしかいなかった200年くらい前は、木でも石でも土でも、要するに自然採集の材料で建築をつくることができた。そのぐらいまでなら環境に受け止められるキャパシティがあった。しかし世界人口がもうすぐ100億人に達しようかという今、自然採集の素材だけではとてもその人口が必要とする建築を作ることはできず、産業的に生産された素材が用いられるようになる。鉄の問題は、こうした構図も視野に入れたうえで認識されるべきことであるように思えるわけです。量としての人間のサバイバルのために必要になった鉄、ということです。その意味では依然として私たちは近代建築の延長線上に今もいる。近代建築について、単に科学技術が発展したことで材料が鉄に取って代わられたわけではなく、ましてモダニズムの美学から近代建築が生まれたわけでもなく、人間が増えたことで自然採集素材から産業生産素材への移行が起こり、そうして近代建築が生まれたとみることができるでしょう。そこで問題なのは、いわゆる知性としての人間ではなく、ただの量としての、ただの生命体としての、極端に言えばバイオマスとしての人間です。そういう身も蓋もない現実からみないとこの問題の全貌はみえてこないように思えるわけです。
青井──日本近代史が専門のジョルダン・サンドさん(Jordan Sand、1960-)によると、バイオマスの意義を捉えた都市研究の先例も決して少なくないそうです。バイオマスとは生物の総量という意味ですが、例えばさきほどのシカゴを、生物やその加工物を含む物質の流れという視点からみることで、都市とそれを包含する広い領域の歴史を描く研究があることを教えてもらいました(William Cronon, Nature's Metroplois, Chicago and the Great West, W. W. Norton, 1991)。人間も量という側面からでないと見えてこないことがあり、ほかの生物量のマクロ・ミクロな流れをつくってその量を支えてきた、ということですね。サンドさんはこうした研究動向に与しながら、同時に、彼の造語である「テクノマス」、つまり人工物の総量を推計して関係づけるような研究の必要性を提唱しているそうです。例えば17世紀江戸のテクノマスと21世紀東京のテクノマスはどう比較可能か、というようなこともそこには含まれると思います。
日埜──マテリアル・カルチャーへの着眼は、意味の水準ではなく即物性の水準に焦点を置くわけですが、まさにその水準で、藍藻が地球を変え、人間も地球を変え、人間自身も否応なく変わった。これらは即物的な水準において本質的には違ったことではない。そうして、10万年前の人間と私たちは振る舞いも違うし、移動やコニュニケーションの量も違うし、環境に対するインパクトだってもちろん違う。ほとんど別種の生命体と言えるかもしれない。そのときにその人間がなにを意思しているかよりも、正面からは意識されない即物的な変容が重大な意味を持つのかもしれない。そういう変化を遂げつつサバイバルする切羽詰まった模索が人間の常態で、調和的な循環のイメージを描いてもなかなかそうはならないんじゃないかというイメージが僕にはどうもあるんですね。どうもSFめいた飛躍の多いコメントになりますが、とりわけ量としての人間の即物性のいかんともしがたさをちゃんと考える必要はあると思います。
中谷──今のお話はとてもよくわかります。人間の未知の生存可能性のほうに話を振っていかないと今後の議論もなかなか立ち行かないと思います。まず生環境環を円環で示したために、また原理0に戻るような印象を与えてしまったら、私の作図能力の不足です。原理4は0を前提とした原理3までのベクトルを変えて、まさに日埜さんのいうようにドリフトさせることで賛成です。
一方で、人間が増えていくことはけっして自然の成り行きではありませんよね。というのも、鉄による高密度集住が可能な人間生活の器としての大都市ができたから人口が増えた可能性もありますし、こうしたことはジャレド・ダイアモンドを始めいろいろな人が仮説を立てていますから、それらを先行研究として吟味しつつ次第に明らかにしていけばいいような気もします。
松田──先に示した生環境の環[fig.3]についてもう少し付け加えておくと、原理4から0に伸びる矢印の先は、決して、原理0から1への循環の起点に戻ることを示しているものではありません。生環境の原理4はあくまで原理0との関係の高次の回復を目指す、ということですから、この生環境環は単に再帰的ないし完結的な環ではなく、原理0をたびたびくぐり抜けながら、螺旋状に立体化されることが探られていく環だと考えるとよいのではないでしょうか。
それから、鉄などを例にとると物質循環的な話も比較的うまくできるわけですが、その循環をイメージするためには、原理0すなわち地球とは、これまでの科学的知見の集積によって認識される存在である必要があります。そうすると、それ以前の歴史段階の人の営みのなかにおいていかに原理0がみとめられてくるのかということや、またそれとは別に、科学的認識それ自体もつねに更新される歴史的諸段階のひとつであることを考え合わせると、人文的な要素も含んだ、より包括的な「原理0」も同時に想定しておくとよいのかもしれません。例えばそれを概念的に「大地」などと呼んでもよいでしょう。科学的知見も時には相対化しうる精神的な「原理0」も想定すると、原理4の原理0とのサイバネティクス的結ばれ方なども、科学と哲学の両面から育めるように思います。
塚本──「大地」というのは比喩的な意味ということですか?
松田──ええ、比喩的な意味も、純粋に物質から構成された実体としての意味も、両方まとえるでしょうね。比喩的な側面では、地球の広がりや深部、そこに関わる時間と空間の途方もなく大きなスケールへのアクセスを人がその日常から想像するときに、多少は感じとることができたり、また一方では追いつかなかったりするような得体のしれない捉えにくさや、あるいは、土地への帰属感や愛、畏敬、畏怖といった生活文化的な側面も、「地球」というよりは「大地」といった概念に託されそうだと思います。
日埜──鉄について、じつはなかなか腑に落ちないことがあって、というのも地球の中心部はものすごい量の鉄から成り立っているらしい。そういう巨大な鉄の塊を含んだドロドロの表面に卵の殻のようにケイ素でできた地殻がはりついている。そっちの方が軽いから浮いていて、そこが我々が生きている場です。恒星のなかで起こっている核融合反応からいろんな原子が生成されるけど、その反応から最もたくさん生成される原子が鉄で、だから宇宙にはそもそも鉄がたくさんある。地球の表面は岩石で覆われているからそう思わないけど、地球は真ん中に巨大な量の得体の知れないような鉄をかかえている。なにか意識と無意識の関係のように。この不気味な鉄ってなんなのか。
中谷──とても重要な指摘です。じつは鉄鉱床との遭遇時にすでに、これで宇宙に行けると考えた人たちがいただろうと感じたのはそこなんです。まだ「卵の殻」の部分を扱っていた文明のなかで、偶然「黄身」を見つけてしまった人がいて、そういう人がその黄身の持つ膨大なエネルギーと可能性を感じた。すくなくとも地球が、卵の殻としてだけではなく内燃機関を持つガソリンのように考えるパラダイムチェンジが起きた。つまり、地球をそれ自体が消費可能なエンジンと捉える原理3の考え方が、300年ほど前の段階で本格化されたとも考えられるんじゃないですかね。
- 獲得されるものとしての生環境/生環境環と5つの階梯/原理3の現れとしての鉄鋼(都市)/原理4へ──生環境環への批判的再帰
- 下部構造としてのEarth Life Mode/「量としての人間」が変えるもの
- なぜ「地球の声」か/空間論の逆使いで取り戻されるもの/連関を留めるものとしての叙事詩/空間論から離れて考える
- 建築デザインをいかに生環境につなぐか/地球の有限性と物質の再配置/人間に現れる「地球の声」の形/生環境環の不可逆性
- 200℃までの世界──川合健二のエネルギー理論/ハンナ・アーレントの「Worldliness」/福島──個人に委ねられる村の行方
- ティモシー・モートンの「とりまくもの」/グレート・ブリコラージュ──原理4に向けて


