対談:空間と個と全体──コモナリティのほうへ

- 篠原雅武氏(左)、塚本由晴氏
戦後建築・都市・空間
塚本由晴──今日はよろしくお願いいたします。すこし自己紹介をかねてお話をさせていただきます。私は日頃個人住宅を多く手がけていますが、一方で学生時代から都市空間そのものに関心があって、東京の街にある、ヨーロッパ的な価値観からはちょっと理解し難いような建物を収集・調査した『メイド・イン・トーキョー』(アトリエ・ワン、鹿島出版会、2001)を皮切りに、都市の空間研究のようなことを継続的に行なってきました。個人−住宅−都市の関係を考えるなかで、今日お話ししたいことにつなげれば、私は個人という概念の持っている頑なさ、自分で自分の境界を引いていくようなあり方とは逆の方向性によってできている空間・場所が好きで、建築でもそういう感覚を実現したいと思っています。こういうことが現代の日本の建築界においてどういう意味をもっているかを最初にお話しようと思います。
- 貝島桃代+黒田潤三+塚本由晴
『メイド・イン・トーキョー』
(鹿島出版会、2001)
このような建設活動に対して政治は防火、耐震、日照、衛生などの性能の基準をつくりましたが、建築物の形式や様式に関しては直接的な介入を避け、個人、民間の裁量に委ねてきました。特に第二次世界大戦直後は国全体が疲弊しきっていて、かつ連合国軍占領下という状態であったため、実行可能な計画案を立てることも、現状に介入することもできず、とにかく自助自立できる人から自分で家を建てやすい環境を用意することが優先された。それが現在のネオリベラリズムとも思われるような都市と建築の関係の端緒となったと思われます。それぞれの土地の所有者は、法規に抵触しない限りどのような建物でも建てることができる。そういう枠の中で、活発な建設活動が経済発展を後押しすることになりました。そして住宅金融公庫と確認申請を連動させる制度をつくることで、個人住宅が最も小さな単位の建築として大量に生産され、建築家が民間の住宅を設計することがあたりまえになり、中産階級でも建築作品の住人になれる環境が広がっていきました。そこは一種の実験場で、さまざまな個性豊かな建築家が現われ、現代のような状況へとつながってきました。もちろん丹下健三さんのようにエリートとして都市計画にも関わり、国家的な大型プロジェクトを主導した建築家もいるわけですが、住宅建築による民間の小さな建築の試みがなければ、世界的にも卓越した今日の日本の現代建築は生まれなかったと思います。
個へ向かう70年代
──フォルマリズム・タイムレス・脱コンテクスト
塚本──ところが、70年代に入ると、時代の雰囲気が変わりはじめます。第二次大戦後の「建築」は新しい民主主義社会を構築するための手段として建築家に信じられ、行政に期待され、人々もそれに共感しようとしていた時代だったと思います。メタボリストたちはまさにそのなかで登場した若きヒーローだった。それが70年の大阪万博を境として官僚主義的なものへと近づいていって──官僚の保守化がはじまったこともあると思いますが──、建築家のなかにも行政のエージェントであるかのような、あるいはテクノクラート的なふるまいが現われ始める。これに対し、60年代後半の学生運動などの余韻も残るなかで、一部の建築家は個に軸足を据えた建築のあり方を模索していくことになります。特に磯崎新さんと篠原一男さんは楽観的に社会なるものを前提にする建築表現に対し、強い批評意識を持っていた。彼らの思考の中心にあるのはフォルマリズムで、建築に内在する言語的、文化的な構造へと遡行し、それに個として対峙することで、個人の衝動と建築表現の自律性を担保するというものです。そこでの建築の価値は、もはや一時的な経済ブームや国家建設のタイミングに左右されない、脱コンテクスト化した、タイムレスなものになります。
磯崎さんの「都市からの撤退」(「見えない都市」『展望』1967年11月号、筑摩書房)は、都市と建築の接点はもう不可能、ヨーロッパ的な都市概念はもはや成立しないのではないかという感慨をロサンゼルスでの都市体験をもとに謳ったもので、いまこそ都市と建築を切り離し、もっと人間の存在・実存に直接向き合う、個に対峙する空間というものをつくっていくということを意味していました。また、もともと数学科出身で東工大に転学して建築を始めた篠原一男は、住宅作家であった清家清に学び、初期の清家が極めて個人的な空間(例えば自邸《私の家》のような)を主な創作の舞台としていたこともあって、個の方へ向かっていった人です。
建築の実践が、それまでの共同体や国家を根拠にしたものから、個を根拠にしたものになり、それにあわせて建築の表現においても建築家の個性が大きく扱われるようになりました。図式的には世界中で同じようなことが多かれ少なかれ起きていたのですが、個人住宅をたくさんつくる産業としての環境があったためにそれが具体化したのが日本とアメリカで、その状態をさらに維持して今日まで展開してきたのが日本なのです。
磯崎−篠原が共有していたフォルマリズムによる脱コンテクスト化と、それを受け止める個の根拠化という仮説は、その次の世代に多大な影響を与えましたが、80年代後半のバブル経済のときに、消費社会化の波を受けて、かなりの建築作品が単なる差異化のゲームに飲み込まれていきました。個を根拠にするという仮説が大衆化したとも言えます。それは建築家の作品のみならず、一般の民家にも広がっていきました。背景には建設技術の合理化やメインテナンスがいらない新建材の開発が行なわれ、建物を建てるときの選択肢の爆発的増加がありました。その結果、一つひとつの住宅は技術的にはしっかりつくられていながら、それらが反復し集合した姿はまるでスラムのごとく乱雑で、説明する言語がない都市空間が出現した。どうしてこんなことになっているのだろうというのが、私の学生の頃からの疑問でした。
私が建築を学んだのは篠原一男の教え子の坂本一成先生の研究室ですから、そこにいる学生はもちろん篠原一男の表現と言説の変化をずっと追いかけていました。その一方で研究室のなかには、「個を根拠にした建築創作の仮説はもう頭が天井についているのではないか?」という疑念も確かにあったように思います。坂本先生の言葉に「環境としての建築」、「建築の構成」あるいは「建築の社会性」というのがあるのですが、そうした言葉もその疑念を反映したものであったと思います。そういう環境で学んだ学生時代から、脱コンテクスト化と個の根拠化の仮説から、どうやって転換するかという問題に、自分は取り組んできたのではないかと思っています。
いま、「共(コモナリティ)」のほうへ
塚本──単に仕事の種類で言うならば、丹下の国家的建造物に対する篠原の個人住宅は、「公−個」あるいは「公−私」という対比の図式で捉えられるでしょう。しかし私が今考えている建築の可能性は、そのどちらでもない「共(コモナリティ)」にあると思っています。建築物が反復され集合した姿や、その間に生まれる都市のパブリック・スペースなどが、ひとまずそうした展開を支える仕事の種類になっています。私は坂本先生に「建築の構成」研究の薫陶を受けているので、建築に内在する構成の原理やモノとしてあり方から建築を思考する、脱コンテクスト化を方法としては受け継いでいます。でもそれによって浮かび上がる建築の言語的、文化的構造に70年代のように「個(インディヴィデュアリティ)」を結びつけるのではなく、「共(コモナリティ)」を結びつけることに現代の建築の可能性を見ています。先ほどの言い方を真似れば、脱コンテクスト化と「共」の根拠化です。それで、篠原さんとの接点となる問題提起として、日本近代において建築家が関わってきたパブリック・スペースがあまりうまく機能していないことを挙げたいと思います。たとえば市庁舎をつくる際に「広場」という概念を持ち込んで、ぽこんと空いた空間が用意されている場所が全国至る所にありますが、実際それがいきいきと使われている例は少ないですよね。なぜなら「広場」はそのようにしてできたものではないからです。系譜学的には広場はヨーロッパ的なもので、街の中心に教会があり、コミュニティに属する人々が集まり、商店が並び、外の人間も訪れる市が立つというような連環のなかで成り立ってきた。結果的にはそれがコミュニティを象徴するものになることはあっても、象徴がいきなり投入されることでコミュニティが成立するわけではない。だから戦後民主主義を象徴する場所として広場を導入したところでいきいきと使われるということにはならないのです。広場はそれを利用する人々のふるまいとの関係を抜きには成立しえないのですから。

- 篠原雅武『公共空間の政治理論』
(人文書院、2007)
私が「共(コモナリティ)」と呼ぶものを、篠原さんは例えば『公共空間の政治理論』(人文書院、2007)で「間」と呼んでいますが、そこでは個でも公でもない「間」がなければ、公も個も成立しないとされていますね。では日本の哲学の分野で実際のパブリック・スペースはどう捉えられてきたのでしょうか?
篠原雅武──例えば、齋藤純一さんの『公共性』(岩波書店、2000)には、日本において公共性という概念がよく言われるようになったのは90年ぐらいからだと書かれています。公共というのは60−70年ぐらいまでは「公共の福祉」を意味する言葉でした。当時「公共の福祉」という領域が可視的に存在していて、逆にその秩序を乱す行為を「公共の福祉を乱す」と呼んでいたわけです。すなわち、公共=国家で、これと私的な存在が対峙するという構図です。
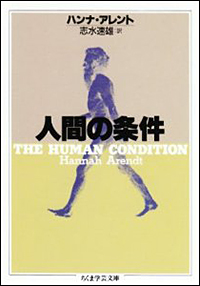
- ハンナ・アーレント『人間の条件』
(志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994)
塚本──そうですよね。『メイド・イン・トーキョー』に載っている物件は90年代に集めたものですからね。『メイド・イン・トーキョー』で集められた物件の面白さは、都市における人々の空間実践が建築デザインや建築計画学というフィルターを通さずに直接露出しているところですが、それを通覧することで、こういう建物を許容する都市として、東京をとらえようとしました。

- マイク・デイヴィス『スラムの惑星』
(酒井隆史+篠原雅武+丸山里美訳、
明石書店、2010)


- グランフロント大阪(2013)
「現れの空間」性のある公共性の議論
塚本──アゲる音ですね(笑)。公共性を具体的な空間性を持つものとして捉えるというのは、非常に大事だと思うのでお聞きします。〈空間性のない公共性の議論〉と〈空間性のある公共性の議論〉というのはどの辺りが違うんでしょうか。篠原──「公共心」や「ボランタリーな精神」のように、ある種のコミュニティへの愛着をもとにして公共性を成り立たせようという試みにおいては、かならずしも、〈公共性の空間性〉が考慮されているとはいえません。それは、精神論的な公共性です。日本における90年代以降のNPOの多くは、そのような公共性に、理論と活動の根拠を定めていると思います。精神論的であるがゆえに、それらは、道徳や倫理を重視するものとなりがちですが、そうであるがゆえに、コミュニタリアン的で、ともすればナショナリズムとも親和性をもつものとなりかねません。
しかし「公共性」とは、そういった精神論的なものとして成り立つものなのでしょうか。私はそのような道徳や公共心に依拠する価値観を共有していなくても公共性は成り立つだろうと考えているのですが、そのような思考は、塚本さんの「ふるまい」へのまなざしとの共振性を持っているように感じます。アーレントも、公共空間というものは、パブリックな活動によってつくられると述べています。ただし、パブリックな活動は、投票行為とか、あるいは街頭でのデモ活動など、いわゆる政治的な活動だけをかならずしも意味するのではありません。アクションというのは、日常の些細なふるまいでもあります。喫茶店で紅茶を飲みつつ談話するとか、公園で子どもと遊ぶとか、駅のホールで人を待ちつつ立ち話するとか、そういうこともアクションといっていいでしょう。公共性とは、こうしたアクションが起こっているようなところにできあがってくるような、空間性をもつもののことです。中国の映画監督である賈樟柯(ジャ・ジャンクー)が『イン・パブリック』という映画で捉えたのも、日常的な些細なアクションが散発的に営まれつつ、その折り重なり、共振において形成される空間的なものといえると思いますが、それを彼は、「パブリック」と命名したわけです。
また、この空間をアーレントは、「現れの空間(space of appearance)」として提示します。「それは、私が他人の眼に現われ、他人が私の眼に現われる空間であり、人びとが単に他の生物や無生物のように存在するのではなく、その外形をはっきりと示す空間である」(『人間の条件』ちくま学芸文庫、320頁)とアーレントはいいますが、つまりそれは、活動が目に見えるものとして、触知できるものとなって現われているところに形成される空間のことです。なにかをするということ、その振る舞い、仕草、息づかい、目配せといったことが、そこにいる人々のあいだで共有され、折り重なっていくところに形成されてくる空間的なもの、ということです(この空間でのやりとりは、インターネットでのやりとりとは違います。現れの空間においては、何かをしたり言ったりするとき、そこに現れている相手の表情や、仕草などに配慮するということを伴いますが、これに対してインターネットは、そういう配慮なしに、何かを発信する場です。こうした現れの空間における振る舞いや配慮といったことは、インターネットというオンラインの世界が成立した結果、かえってその重要性がクローズアップされることになるのではないかと思われます)。たとえば喫茶店でしゃべっていても、議論が活発になることによって、公共的な空間性が立ち現われてくると考えることができるし、逆に言えば、物理的な公共空間として建築空間(塚本さんが先ほどいわれた「ぽこんと空いた空間」のようなもの)が用意されていても、人がまばらで、活動が活発でなく、何も起こっていないなら、公共的でない、死んだ空間になっていると考えることができます。活動が活発であることの度合いと空間の公共性の度合いが相関関係にあるという観点から、公共性を考えなおすことが必要ではないかと考えています(ただ、ちょっとだけ付け加えておきたいのは、議論が活発であるということは、かならずしも、声が多数交わされ、音としてよく聞こえているということを意味せず、べつに静かであってもいいと思います。沈黙、静かな思考をも許容する空間、沈黙から聴き取ろうとする営みが主となる空間。「個」として、「私」として閉じた人たちが多数集まり、思い思いに発される声が充満していく状態を、はたして公共空間といっていいのか。そのあたり、丁寧に考える必要があるかもしれません)。

- アンリ・ルフェーヴル『空間の生産』
(斎藤日出治訳、青木書店、2000)
塚本──身体が具体的な場所を占めてしまう以上、それは空間とは切り離せない概念だと思います。建築における空間を考えると、例えば幾何学的な秩序に偏ったフォルマリズムの場合、身体は原理的には必要ないことになり、外部との応答なしに成立する世界をつくってしまう。しかし実際にわれわれが経験すること、そして建築をつくることはそれを大きく超えています。良い建築とは間違いなく身体性とそのふるまいに対する繊細な配慮があるものであることがわかっていながら、建築を理論化しようとすると、そこに統合しにくい身体性やふるまいが排除されることになりがちなのです。
現在の日本では、個々の建物が外の通りで起こるふるまいに対して、ほとんど想像力を持たない家が建てられています。窓も小さいので道を歩いていても人々が家のなかで何をしているのかわからない。また人々は昔のように、自分が住む街での建物の形式を知らないので、メーカーが供給するものからなんとなく選びとるしかない。結果はバラバラになります。そこでよく言われるのが「個と個をつなぐ空間」の必要性です。ここでいう「個」は家の中の個室である場合もあれば、ひとつの住宅を指す場合もあります。しかし、注意しなければいけないのは、その言い方は無意識に「個」という単位は揺るがないことを前提にしています。しかしそれだって歴史的に形成されてきた認識のはずです。とくに、近代化というのが住居の空間にもたらした変化が、その形成に大きな役割を果たしてきました。
伝統的な農家の田の字プランや非常に狭い長屋からの生活改善として、近代・戦後を通して食寝分離、個人の空間の確保を進めてきた経緯があります。現在の居住空間が歴史的な段階を経てきたことは確かですが、それが居住の最終形態であるかというと疑問で、私は空間単位による個の表象が信じられていることに危うさを感じています。小さな居室で個を担保し、居室間の交通空間で共を担保するというのは数えやすいしわかりやすいですが、それでは個の総和が社会であるとする図式の似姿でしかなく、空間性を伴った公共性にアピールしないでしょう。
そもそもふるまいは社会的なもので、例えばいま50年代の日本映画を見ると、登場する人々の立ち居振る舞いが、現在の日本人とはずいぶんちがうことに驚いてしまう。
篠原──『キューポラのある街』(1962)という映画がありますが、主演の吉永小百合の暮らしている家には個室がなくて、皆同じ部屋で暮らしています。赤ん坊もいれば失業した父親もいて、混沌としているのですが、そんななか、家族の皆がふるまいを共有せざるをえない状況があったということがわかります。
塚本──気をつけないといけないのは、個の確立はその時代に間違えなく要請されたことで、それが無意味だったということではないですよね。
篠原──ええ、ですから個が確立されていなかった時代を今賛美するというのは違いますよね。
塚本──問題は個の確立に向けた動きが、人々の自然な紐帯までも解体してしまうところにまで及んでしまったことです。そういった部分は見直されなくてはならないでしょう。そのきっかけを私はふるまいに見出しているわけです。しかしやっかいなのは、ちょうど個の確立が経済成長、そして資本主義の拡大と重なる時期だっただけに、人々を個へと切り離して行く強固なシステムが築きあげられてしまったところです。
柔軟性と都市文明の危機
篠原──なるほど。じつは私がずっと考えてきたのも、揺るぎない個とそのことゆえの息苦しさという問題だったと思います。私が育ったのは神奈川県のニュータウンの団地で、家のなかは個室で区切られているし、家と家の繋ぎ目となる廊下や階段、団地と団地のあいだにある公園や街路といった空間は、あまり居心地のよいものとはいえませんでした。家族は核家族として確定され、家族の構成員は私室にこもる個人として確定されているために、公共性、コモナリティが成り立ちにくい、ということです。こうした経験を振り返りつついまにして思うのは、息苦しさは、個へと確定されていくことにともなう公共空間の衰退と関係があったのかもしれない、ということです。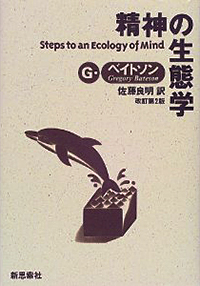
- グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』
(佐藤良明訳、新思索社、改訂第2版、2000)
塚本──2001年に大学院の授業で、渋谷の「パブリック・スペース」と思う場所はどこかと尋ねたら、学生たちから挙がってきた場所のほとんどがデパートやセンター街やカラオケボックスのような商業空間の一部でした。一方的に与えられた場所を個々が消費行為を介して利用する、まさに柔軟性のない空間です。これではパブリック・スペースを使いのめしてつくり変えるような発想にはなかなか至らない。
そこで少し開き直って、渋谷のパブリック・スペースがヨーロッパ的な公準からどれだけ離れているのかを探るために、その場所が用意されている理由や、そこに成立している時間の流れやリズムといったものを調べました。ひとつ見えてきたのは、学生が挙げた渋谷のパブリック・スペースでは、維持監理の責任やデューティから人々が解放されているということでした。もちろんそれを管理する側はそこに直接的、間接的に課金したりしているわけなのですが。これは渋谷が郊外住宅地へとつながる私鉄のターミナルであることと関連があると思いました。郊外住宅地には家や学校があるのですが、そのどちらでも自分の責任を問われます。そこから逃げ出す先が渋谷ということなのだと思います。
一方、2006年のFIFAワールドカップの時に六本木で体験した交差点の使われ方はおもしろいものでした。日本には広場が少ないのでサポーターは歩道を歩くわけですが、信号を待っている間にシュプレヒコールしたり、青に変わった瞬間に双方から走ってきてハイタッチをしたりするんです。交通整理をする警官の笛も祭の囃子に聴こえるほど盛り上がっていました。そういうおもしろい集団的パフォーマンス、しかも普段われわれが使っている横断歩道と歩行者信号だけを遊びのために利用したパフォーマンスが生まれ、乱れることなく続いているということが新鮮でした。パブリック・スペースとは大型商業施設であるというような、都会の人は一方的に与えられた枠のなかでの消費的なふるまいしかできなくなっていくような印象を持っていましたが、こうしたことを見るとそんなことはありませんね。
この例で大事なのは、そこに囲いがない空間ができあがっていたことだと思います。囲いはなくても領域が確定され、内部を感じる状態はどのようにして生まれるのか。たとえば公園で同じ踊りをするための10人が集まって練習していれば、そこに囲いはなくても、その人たちのふるまいの共有によってひとつの領域、ひとつの内側が生まれますよね。必ずしも同じ動きでなくても、ある了解のもとに起こるふるまいが共有されていることで、硬い境界を持たずとも領域を担保できる。 もちろん人のふるまいだけでは建築はつくれません。同時に雨・風・重力といった自然の要素のふるまいに対応しなければならないし、都市空間のなかでの建物のふるまいがある。そういう異なる次元のふるまいに対する配慮を均衡させ、統合された状態を作り出すのが建築の役割だからです。 ふるまいに共通しているのは、背後に時間概念があることです。時間の尺度の取り方でふるまいは変化してくる。短い尺度で観測できる人のふるまいと長い尺度で観測できる人のふるまいは違います。個人の生活の繰り返しは1日という単位でみることができますが、学校や会社は1週間、コミュニティの祭りなら1年といったように、それぞれのリズムや周期によって捉えられるふるまいは変わってきます。自然や建物についても同じことがいえます。朝から昼にかけて陽が差し込む部屋の温度上昇を観察するには3時間もあれば十分ですが、台風を観察するには1年待たなければならない。建物ならもっと長く、50年、100年のスパンで見ることによって、徐々に建て替えられたり、改築されたりして、ゆっくりした周期ではあるけれどふるまいをつくりだしていることが見えてきます。このようにそれぞれのふるまいに固有の時間尺度があるのです。
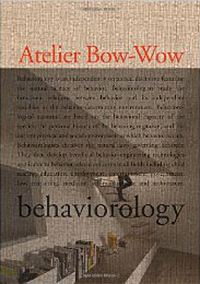
- Atelier Bow-Wow, Terunobu Fujimori,
Washida Menruro, Yoshikazu Nango,
Enrique Walker,
The Architectures of Atelier Bow-Wow:
Behaviorology, Rizzoli, 2010.
篠原──それを踏まえたうえで公共空間づくりを実践されているということですね。
塚本──使う人や住む人の個々のスキルから、人々が集まることで生まれる相互作用までを包括して施設を設計するほうがよいのですが、それは難しい上に手間がかかります。だから世の趨勢として、管理上の合理性や記号的操作による存在意義の表象あたりまででしか施設の設計ができない場合が多く、それが建ち上がると逆に人々に内在する様々なふるまいや、それらの有機的な関係を疎外することになる。これがハコモノ建築として批判されるわけです。なんでそんなことになるのか? 日本では建築が工学として教えられてきたことや、公共建築の建設が主に単年度予算で動かされていることなどにも原因がありそうです。
篠原──それはやはり近代以後の現象なのでしょうか。私が住んでいる大阪の豊中市には、4、5世紀に創建された原田神社という神社があります。境内は大きな広場のようで、犬を連れた人たちが集まったり、散歩コースになっていたり、子どもが遊んだり、フリマやお祭りに使われたりしています。神社やお寺はこういう空間の公共性を感じさせますよね。こういう空間をつくりだすのは、近代以前は可能だったけれども、現在は難しくなっているということなのでしょうか。
塚本──神社や寺には可視的な歴史がありますが、たとえば新興都市の新しい行政施設前の広場などは歴史とは無関係につくられてきたものが多いと思います。調べても歴史が紐解けない場所などないはずですが、新興を謳う街の新住民にとって関心は利便性などであって、土地の歴史はあまり関心の対象ではなく、そのために愛着も生まれにくい場所になる。
戦後の郊外開発の多くは徹底的にそのような意味での歴史への配慮に欠けていたと思います。短期的観測にもとづく量的供給や利便性を優先して、ほかの価値を認めていない。だからその先に立ち上げるものがないわけです。非常に対比的ですが、西洋の歴史的な中心市街地には古い建物が残されていて、それを維持することの価値が持続しています。新しい建物を建てる際には、古い建物の形や様式、材料に学ばなければならない。建築は歴史が物質化したものであり、その物質の現在的な取り扱いが社会規範を組み立てるうえでの大事な道具になっている。すると自分たちの街、建築についての自立的な認識と自信が育ち、全体性が維持されます。その反面として、ひとつの建物を建てるプロセスも長く、手間もかかってしまい、途中で建物を建てるのをやめざるをえない状況に追い込まれることも多い。
結局日本の都市はそこを解除してしまったのですよね。大震災や大戦で都市が燃え尽くしてしまったことの意味は大きいですが、戦後は特に、古い建物の維持保存は経済活動のブレーキと見なされ、新しい建物を建てる方向に社会全体が舵をきってしまった。そのブレーキを外すことによってGDPが最大化したことは事実でしょう。しかしそれをやったことによって、建築や都市を通して自然と培われるはずの、個である人間を越えたスケールを共有する感覚、物質化された歴史に支えられ、寄り添っている感覚、集団が歴史的な継続性や全体性と一緒にあるというような感覚が希薄になってしまった。
オリンピック・パラリンピック
──30日間のための都市開発?
篠原──ベイトソンも、短期的に利益が得られる方向でハードにプログラム化して都市開発を進めてしまったことを批判的に捉え、それが破局への途であると指摘しています。長期的なヴィジョンを持つことと柔軟性を保持することがリンクしているにもかかわらず、日本の社会ではそれが同時に失われているのだと思います。ある時点から短期的になってしまったのでしょうが、もしかしたら、私たちはいま、その行き着く先まで来つつあるのかもしれません。
梅田駅周辺では、「グランフロント大阪」のほかにも再開発は進んでいますが、それも結局は、そうした短期的で柔軟性を欠いた趨勢を押し進めるものでしかないと思いますし、30日間のオリンピック・パラリンピック大会、それにともなう3兆円といわれる経済効果のために短期的に都市をつくりかえるという話もまた、柔軟性と長期的ヴィジョンが失われていることの典型ではないでしょうか。短いスパンで経済効果を出すために都市をつくりかえよという要求が、日本の都市部で蔓延しているように感じます。
塚本──経済的負担は時間を短くすることによって軽減されるという性格があるので、「時短」と「経済効果」の結びつきは強固ですね。あらゆることが「できるだけ早く」と要求されることになる。都市や建築との関係で考えた場合、短期的観測を受け入れざるをえないオリンピック・パラリンピックというイヴェントをどれだけ長期的視点に立って位置づけることができるかが問われるのでしょうね。2012年のロンドン・オリンピック・パラリンピックは長期的な出口戦略も立てて、例えば、重工業の繁栄と衰退に伴って土壌汚染や環境悪化を深刻化させた、テムズ川流域ドックランズなどの地域の産業構造の転換を再開発を進めることで行なおうとしていて、都市の文脈にオリンピック・パラリンピックをうまく乗せました。むしろ東京の問題は、そうした中長期のヴィジョンがほとんど見えてこないことではないでしょうか。開催地に選ばれてからの話なのかもしれませんが、30日間にすべてを蕩尽してはまったく意味がありません。
篠原──30日間という短期間のイヴェントのためだけの都市開発とは、なんとも不条理な話です。結局、経済効果が目的であって、そこで実際に何がなされるかということについては、じつはあんまり配慮していないように思われてしまいます。その結果として立ち現われる都市はおそらく、その短期性、硬直性ゆえに、儚くて、スカスカしたもの、実在感の乏しいものにしかならないのではないでしょうか。まだ数年先のことですからなんともわかりませんが。
塚本──オリンピック・パラリンピックはさまざまな思惑やリスク、リターンがあるので、統一的な見解を持ちにくいのですが、東京は成り行きで都市計画をやってきた街だからどんな方向に進んでも吸収したように感じられてしまうかもしれません。
こうしたオリンピック・パラリンピック招致による都市改造と対局だなあと思うのが、東北大震災による津波の被害を受けた集落の神社です。今私の研究室では宮城県牡鹿半島の大谷川浜、谷川浜、鮫浦の三集落で復興支援を行なっています。これらの集落では住宅はすべて津波で流されてしまったのですが、神社だけは丘の上にあるために残りました。参道や鳥居は傷み、柱も傾いているところがあるので、その補修計画を立てているところです。大谷川浜には獅子振りという祭りがあるのですが、実は獅子頭も津波で流されてしまいました。集落の人たちは祭りを復活させたいと、日本財団の支援で新たな獅子頭をつくってもらい、6月9日に2年ぶりの祭をしました。津波で残った二渡神社で奉納の儀式を行ない、あとは小さな境内で獅子振りが披露されました(以前は一軒一軒を獅子がまわったそうですが、今はまわる家がありません)。方々の仮設住宅などにばらばらに入居している集落の人たちですが、その日は60人近くが集まりました。そのときの集落の人たちの楽しそうな表情を見て気付いたのは、これこそが幾度もの津波災害を乗り越えて集落を長きに渡り持続させる仕組みであるということです。津波で低地の住宅は流されてしまうけれども、神社は残る。そこに皆が集まり、集落の紐帯を確認する。そして漁さえ始まればまた家が建ち、同じ場所での暮らしが始まる。その繰り返しだと。脆弱性は高いけれど、柔軟性と自律性も高いですよね。公共性や、生身の人間の寿命をゆうに超えていく時間的な広がりを具体的に、物質的に感じることができ、豊かな気持ちになれます。「グランフロント大阪」のような巨大開発の施設よりも、しぶとく持続してきたリアリティがあります。

- 『現代思想』2013年1月号(青土社、2012)
塚本──環境・社会的諸関係・人間的主観性を扱う問題系をフェリックス・ガタリも「エコゾフィ」と題する論文で描いていました(『現代思想』2013年1月号)。非常に示唆的な内容でした。
作法・型、スキル、そして、ふるまい
塚本──古い町並みをずっと維持している岐阜県飛騨古川には、町並みを壊すようなことを「相場崩し」と呼んで戒める習慣があります。自分の住む場所の建築物や町並みの形式、つまり物の扱いを人々が知っている。建築のコモナリティが理想的に現れている例だと思います。篠原──その「相場」はまさに「共」=「コモナリティ」をさす言葉だと思いますが、身体ととりまく世界の物質性が調和した理想的な状態を維持する知恵ですね。例えば「ナショナリズム」のように広漠とした価値観ではなく、身体と物質性との相互作用のなかで出てくる「相場」のような具体性を支えとする概念には強さがありますね。

- 藤田省三『精神史的考察』
(平凡社ライブラリー、2003)
藤田省三が危機感を持ったのは、作法、型の崩壊だったと思います。作法、型は単に頭のなかに存在するものではなく、身体的なスキルとして学ばれていくものであり、他者とのやりとり、ふるまいを共有することで維持されていくものといえますよね。それがスカスカになっていったのが高度成長期だったのではないかと。彼の議論が重要なのは、そうした作法、型の崩壊を、街という環境の変化とリンクさせているところです。漠然と日本的な伝統的価値観がダメになったということではなく、街の変化と対応するようにして作法、型がガタガタになっていく、ということです。それは現在にいたるまで続いているという気がします。「時短」と「経済効果」が強く結託する過程で、ふるまいや作法、型が崩れて、ショッピングモールでの効率的な消費行為の頑ない個人化に行き着いたと。
塚本──特に大都市では、消費のふるまいしか知らない人間が次々と生産されている感じですね。
街の変化は人間精神の変化
篠原──また、藤田省三は、「写真と社会」(『藤田省三著作集』みすず書房、1997)という論集で街の変化をとらえた写真について論じています。そのあたりは、多木浩二の試みに近いものを感じます。彼らのように、時代と街の変化に対して反応しつつものを考え書いていた思想家や哲学者からは、今もなお、多くのことを学ぶことができます。多木と同じく、藤田省三は、ヴァルター・ベンヤミンをかなり読んでいた人です。もともとは、天皇制国家批判や転向論などを主題とする、オーソドックスな政治学者だったのですが、ある時期から、おそらくは70年代なかばあたりから、時代状況にコミットした思考を展開するために、積極的に街に出るようになった。そういうところが独特だと思います。ベンヤミンも『パサージュ論』でパリの微細な変化に着目して哲学的思考を試みていますし、ゲオルク・ジンメルも、ベルリンの街が劇的に変わっていく状況を背景にして独特の哲学的な思考を試みています。メトロポリスが立ち上がっていくプロセスのなかで人間精神がどう変化したかを捉えていくのですが、このように、都市環境の物質的な変化の過程との関連で哲学的・思想的な課題を見出す人たちはいたわけです。話が飛びましたが、やはり思想家や哲学者がそこに問題系を見つけるように、街の変化は人間の精神の変化を伴います。今日の話に戻れば、新興住宅地の建造にともない、都市環境から余白としての空間がなくなっていく時期から、公共空間の衰退や喪失、コモナリティの集団的な忘却が始まっているというシナリオも成り立つのではないと思います。ただ、さきほども話にでましたが、コモナリティの忘却による個人化と、ヨーロッパ的近代を身につけた個人主義とは別種のもので、区別する必要がありますね。つまり、個人化は、他へと開かれた余地のない自閉化ですが、これに対してヨーロッパ的な個人主義は、他へと開かれているし、コモナリティの形成をともなうのではないかと思うのですが、日本では、そうした個人主義の体得を欠落させたまま個人化が進んだといえるのではないかと思います。
塚本──なぜそうなってしまったのかを考える必要があるでしょう。個と全体の関係についての理解が鍵なのではないでしょうか。個とはパイ全体を分けたピースなのか、あるいは個は全体であり全体は個でもあるような相互関係が成立するのか。
近代の集合住宅が物質化している図式が、実は前者の個と全体に近いのです。集合住宅の共有部の空間というは、面積と管理方法とアクセシビリティの関係として、非物質的に定義されています。そこに想定されている住人も、空っぽな人間であって、具体的なふるまいを内在させた人間的な存在ではない。そのために、結局誰も使えない場所になっていることが多い。住人どうしが共有可能なふるまいを見出せれば良いのですが、空間のほうから、無色透明であるかのように扱われるうちに、そのような認識のほうが当たり前になってしまう。
篠原──われわれがそうした場所を使うスキルを受け継いだり体得したりしていれば、その空間をコモナリティの空間として物質化することができるということでしょうね。
塚本──そのとおりだと思います。でもほとんどの集合住宅の場合はそこに誰が住むかわからない状態で設計しなければならない。これはジレンマです。
ふるまいをキャピタル化していくという対抗手段

- 塚本由晴氏
塚本──あ、先ほどのヨーロッパ的個人主義という言葉に促されて「コモナリティ」発現を設計に取り入れることができなかった残念な例を思い出しました(笑)。スペイン・バルセロナの山側に、1930年代にアンダルシアから移民として入ってきた人たちが、アンダルシアと同じ方法で自分たちの街をつくりあげた場所があります。移民によって不法に始まった町づくりですが、やがて権利を認められ、電気水道下水といったインフラが整備され、今では地下鉄が通り、坂を登れない老人のための公共のエレベーターまであります。この地下鉄駅の上、バルセロナ市街地を一望できるところに、新しい広場がつくられました。でもその広場の設計者には、ここにどういう人々が住んでいるかが見えなかったようです。アンダルシアの男たちは鳥を飼っていて、休みの日に鳥かごを持ち寄って見せ合う習慣があります。移民したバルセロナでも同じ習慣を続けています。当然新しい広場でも、これが主たるアクティビティになります。しかし広場はバルセロナの眺めを楽しむようには設計されていても、この鳥かごを持ち寄るふるまいのためには設計されていませんでした。街を見下ろすためのベンチ以外に鳥かごを置く場所が無いので、結果男たちはバルセロナの町に背を向けて立つことになります。そうすると、この習慣は洗練されていない、冴えないふるまいに見えてしまう。彼らにとってこの習慣こそコモナリティの大事な発現なのですから、それが一番よく見えるように広場を設計するべきなのです。
似たような失敗はいたるところにあるので、これを防ぐことが公共空間の設計に必要とされることでしょう。透明な人々のためのどこでも同じ公共空間ではなくて、場所が違えば人々が違うので、求められる公共空間も違っていいはずです。ローカリティや歴史を内包したふるまいに満ちた公共空間に参加することは、人々にとって幸せなことだし、それは結果的に外から訪れた人にも楽しめる場所になると思います。
マネーキャピタルが強くなると同時に地方自治体の税収入が減っていくという現在の状況は、必要とされているところにお金がだせない状況です。お金がなければなにもできない悪い循環です。これに対しては、人々が内蔵しているふるまいをキャピタル化していくという対抗手段があると思っています。

- 篠原雅武氏
篠原──私もひとつ思い出しました(笑)。ハンナ・アーレントの本のタイトル『人間の条件 The Human Condition』がそうであるのは、彼女が結局のところ問うたのは、人間が生きていくことの条件とはどのようなものかということだと思うのですが、彼女がいう「パブリック・スペース」は、いま塚本さんがおっしゃったような意味で捉えてみるべきなのではないかと思います。人間は真空を生きているわけではなく、なんらかの環境を生きているわけですし、われわれの生活のあり方は、その環境がコモナリティを支えるものとして形成されているかどうかに左右されてしまう。昨今盛んに議論されるセーフティネットという考え方も、本当のところはただ経済的な条件を整備すればいいという話ではなくて、生存のための環境条件そのものをどうセーフティにしていくかという議論でなければならないはずです。
塚本──ヨーロッパ、特に歴史の古いイタリアやフランスでは歴史のなかで一番栄えた時期に堅固な建築や都市をつくって、それがいまだに支えになっている。栄華を極めた時期に都市としての卓越が起きて、その後を生きていく人間の支えになっているわけです。これは非常に大事なことだと思います。しかし日本では、戦後復興から高度成長期を経てバブル経済の栄華を経験した80年代後半、いざなみ景気と呼ばれた2000年代半ばのピークに日本の都市にコモナリティの核になるものができていたのかどうか。私の見方では、それらの好景気はグローバリズムや金融資本主義を世界的な規模で肯定し、むしろコモナリティを積極的に外す出来事であった。現在に及ぶきつい社会構造が確実にそのときにつくられたと思います。
篠原──たしかにそうですね。東京オリンピック・パラリンピックがその社会構造を土台として開催されるとすれば、祝祭の裏で、このきつい構造はより強固になり、コモナリティの縮減はいっそうすすむことになるのではないかと危惧しています。
全体性とは何かと問うことは、すべてが連関しているとはどのようなことかと問うことである
塚本──アトリエ・ワンの公共性につながるプロジェクトのひとつに「マイクロ・パブリック・スペース」の実践があります。まず街のリサーチを行ない、直感的につかんだその街の面白さを、人々の独特のふるまい、それを支えている物理的な仕掛けを通して探っていくものです。人は直接人々のふるまいには触ることはできないけれど、それを支えている環境には触ることができる。例えば上海では、自らさまざまに改造した自転車や、道にテーブルを出して料理をしたり、食事をする人々を見かけました。そこからわれわれは自転車と家具を組み合わせた作品《ファーニ・サイクル》(2002)を作りました。路上でお茶を飲んだり料理をするふるまいは、囲われていない空間のなかで成立しているのでふにゃふにゃしたテンポラリーなものですが、人々のなかに実行するスキルがあるので、上海の街に《ファーニ・サイクル》を放つとそれがどういう使い方をするものか、すぐ理解してもらえる。でもいつもの見慣れた自転車とはと少し様子が違うので人の渦ができ、小さなパブリック・スペースが生まれるわけです。まちの道具を変えることで人のふるまいに介入することを実践するプロジェクトです。いろいろな都市での様々な実験を通して、ふるまいの集中が起これば、空間性のある公共性を見出すことができることを学びました。ここで問われるのが中心性、セントラリティの問題です。ふるまいを共有することは、そこに自分たちでセントラリティをつくっていく可能性をも意味します。それは祭のようなテンポラリーなものでも構わない。このセントラリティについては、言論のレベルでも探求して救出する必要があるのではないでしょうか。



- 上海の自転車交通とアトリエ・ワン《ファーニ・サイクル》
篠原──それはまさに私が仕事としなければならないことですね。先に挙げられた『現代思想』同号の鼎談「『破局』の『全体性』の只中で思考しつづけるために」でも論じたのですが、現代において、どのようにして「全体性」の重要性を言うかが課題だと感じています。ティモシー・モートンは、『The Ecological Thought』(Harvard Univ. Press, 2010)で、エコロジカルに思考することの意味を考えています。彼は「エコロジカル」に思考することが、「一なる」自然との調和というのではなく、自分たちの行為が、私たちをとりまく世界を満たすさまざまな物事と相互に連関していると考えることだと述べています。全体性とは何かと問うことは、すべてが連関しているとはどのようなことかと問うことである、と。この本は2010年に刊行されたのですが、私はモートンの一連の思考が、00年代に進行した事態に対する反省的なものではないかと考えています。彼は経済成長が、世界を「全体性」という観点から考えることを不可能にしたと言っていまして、その点からいえば、先程から言われている高度成長の過程で個が重視されていった状況は世界的なものだったのでしょう。人文社会系でも80年代から「差異」という概念がキーワードになりましたが、それは表層的には消費の欲望喚起を正当化し、さらに個の重視を強固に進めていくものとして流通することになったのではないでしょうか。差異の重視には、解放という側面がある半面、個への分断を引き起こしていく契機があるともいえると思います。消費資本主義のもとで差異の概念が肯定的に使われ、結果として個人化が進んだということの問題性を、現時点から、あらためて反省的に考える必要があるのではないでしょうか。これに対し、「差異」を頭ごなしに否定するとか、コミュニティの意義を説くといった極論に陥るのではなしに、相互連関としての全体性とはどのようなものであるかを考えることが求められていると思います。
塚本──消費が生み出す差異化は資本主義の仕組みのなかでもう一度均質化するという考え方もありますよね。労働時間のなかで労働して、給料を得て消費をする、それによってもう一度つながることができる。横につながるというよりは、上から与えられたシステムに自らつながると言えるのではないでしょうか。漁村へ行くとそれとは違う図式の中で人々が生きているのが面白いんですけどね。漁村には資本主義的な価値ももちろん入っていますが、一方で魚屋はないので、漁師だけでなく、公務員でも魚を買ったことがない人が大勢います。都市生活者は個を空間的ではなくシステム的に位置づけているので、システムがなくなったときにパニックになる。システムは上から吊り下げられているものですが、空間にはネットワーク的な迂回路があるから、すぐにパニックになることもないのです。
篠原──相互連関のなかでこそ、個として生きていられるというわけですよね。上意下達のシステムのなかで、思考停止した状態で安穏と生きているかぎり、相互連関は見えてこないし、そういうことへの感覚も摩耗してしまう。そういった、システム的なものとは異なる意味での、相互連関としての全体性についてなにか言えないかと考えています。これが私たちの生存の支えとなる、そのようなものとして、「全体性」を考えてみたいです。ベイトソンはもちろん、モートンも人間を取り巻くものとしてエコロジーを考えることを提唱していますし、ジェイムス・ギブソンがいう、環境内存在として人間を考えるということも、われわれを取り巻くものとしての都市環境の質感、コモナリティを問うきっかけを与え続けている。そうしたところで相互連関の意味合いを考えることから、個としての成長、つまりは個人化の頑なさからの解放の条件が何であるかという問いへの解答が出てくるのではないかと思います。
塚本──相互連環のなかに位置づけられていると、それを維持することに責任を感じ始めると思います。空間と切り離されたシステムのなかにあっては、責任を持つことができない。相互連環のなかに生きている感覚は、場所や物、空間の維持や持続性の重要さを感じることだと、漁村に行ってひりひりと感じました。また相互連環のなかでの仕事のあり方は分業型ではなく協業型だから、ひとりが何役もやるんですよね。人口は50人しかいないけれども仕事の手は延べ200人分あるというような面白さがあります。海、山、田んぼにそれぞれ自分の活動の種が置いてあるというのはすごく豊かですよね。
篠原──経済的な豊かさの指標としてGDPがあって、われわれはその豊かさしかわからなくなっている面があるので、漁村にあるような相互連関を生きている状態もまた豊かであるということを言っていかなければならないと思います。
塚本──ええ、しかしそれを都市化するとどうなるかは難しい問題であり課題ですよね。
篠原──近代の社会科学は、方法的個人主義という言葉が示すように、個がその基礎的な単位です。集団を考えるときも個の総和だったわけですが、これに対し、あらためて問うてみたいのは、個の総和としてではないやり方で全体をどう考えるのか、ということです。そうなると近代社会科学の前提を問い直さなくてはいけなくなるのですが、それはまた別の機会に考えましょう。私がひとつきっかけになると思っているのは、さきほども言ったとりまく世界の物質性の議論を継続していくことです。ベイトソンやドゥルーズ=ガタリ、モートンらの仕事に通底しているエコロジー思想を現代にどのように捉え直していくかも課題です。まだまだばらばらな状態で考えていますが、いずれ、何かまとめていかなければならないと考えています。
塚本──感覚的にどういうことかというときは、アトリエ・ワンがアシストします(笑)。
[2013年9月7日、大阪水交ビルにて]
塚本由晴(つかもと・よしはる)
1965年生まれ。東京工業大学大学院准教授、建築家、貝島桃代とアトリエ・ワン主宰。最近の作品=《ハウス&アトリエ・ワン》(2006)、《みやしたこうえん》(2011)、《BMW Guggenheim Lab》(2011)、《Rue Ribiere》(2011)ほか。最近の著書=『空間の響き/響きの空間』(2009)、『Behaviorology』(2010)、『WindowScape 窓のふるまい学』(2010)、『A Primer』(2013)ほか。
篠原雅武(しのはら・まさたけ)
1975年生まれ。大阪大学特任准教授、社会哲学・思想史。著書=『公共空間の政治理論』(2007)、『空間のために──遍在化するスラム的世界のなかで』(2011)、『全−生活論──転形期の公共空間』(2012)。



